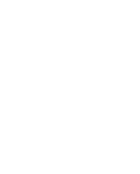検索結果一覧
65件中21件目から30件目を表示しています
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
都市街区を考慮した光環境シミュレーションの導入による ESとCFDの連成解析の高度化に向けた基礎的検討
- 研究者名
- 山本 竜大
- 所属組織
- 久留米工業大学 建築・設備工学科 助教
- 助成金額
- 150万円
概要
建物周りの都市街区の有無に応じて室内側の熱環境には相違が生じる。例えばEnergy Simulation (ES)では一般的には、都市街区の日射の影響は考慮しない。実際には日照面・日影面で相違が生じるため考慮する必要がある。特に都市街区の影響は隣棟間隔にもよるが、非常に重要な要素である。都市の解析はComputational Fluid Dynamics(CFD)でも行われているが、室内側の計算はESに頼るのが現状である。また、室内側の室温を非定常に精緻に解析する手段としてESとCFDの連成解析が存在する。
そこで本研究では、都市街区をモデル化した際の日射の日照面・日影面のESとCFDの連成解析に与える影響に関して基礎的検討を行う。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
地球温暖化防止と資源有効利用のための低炭素型建材の性能評価
- 研究者名
- 寺井 雅和
- 所属組織
- 近畿大学 工学部 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は,環境負荷低減,産業廃棄物の有効活用の観点から,これまで建設材料として広く使用されているコンクリートに代わる,ジオポリマー建材の開発を行った。ジオポリマーの作製に用いる主原料として,活性フィラーは高炉スラグ微粉末,アルカリ溶液には水ガラスを用いて,ペースト,モルタル,コンクリート供試体を作製し,水ガラス水溶液濃度が圧縮強度に与える影響を実験によって調べた結果,以下のことが明らかとなった。ジオポリマーの単位体積質量は,セメント系硬化体とほぼ同程度である。単位水量と強度との相関性は見られず,水量が増加しても流動性は高くならない。表面から内部にかけて緑青~紺・黒色が認められ,色が濃くなるほど強度発現は大きい。Caを多く含む高炉スラグ微粉末ベースのジオポリマーでは,白華が生じやすい。本研究の結果,ジオポリマーは将来コンクリートの代替材料になる可能性があることを確認した。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
都市化がもたらす生物の形質へのインパクトの評価
- 研究者名
- 高橋 佑磨
- 所属組織
- 千葉大学大学院理学研究院 特任助教(千葉大学大学院理学研究院 准教授)
- 助成金額
- 150万円
概要
近年、人間活動が原因となり生物の生息地の生物的・無機的な環境は急速に変化している。都市化は、急速な環境変化の代表例である。都市では温度上昇や光害、騒音といった環境変化が起き、このような環境変化が都市の生物にさまざまな影響を与えていると考えられている。しかし、表現型レベルでそのような影響を評価した研究は稀である。本研究では、果樹害⾍のオウトウショウジョウバエDrosophila suzukii)を用いて、都市化に伴う表現型の進化的、可塑的変化の成否を多角的に検証することを⽬的とした。その結果、温度耐性が都市-郊外勾配に沿って有意に変化していることがわかった。また、夜間に微弱な人工光を当てて飼育すると、成虫の活動量が著しく低下することがわかった。これらの結果は、温度耐性や日周活動パターンが都市化に伴って進化していることを示すとともに、温度や夜間の照明の変化が本種の活動に多大な影響を及ぼしていることを示唆している。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
健康都市づくり!先進的緑道網の構築戦略策定
- 研究者名
- 石松 一仁
- 所属組織
- 明石工業高等専門学校 都市システム工学科 助教
- 助成金額
- 147万円
概要
緑道(greenway)とは,環境負荷が少ない交通網と生物の生息地相互の連絡機能を兼ねた歩道・自転車道及びそのネットワ-クのことである.言い換えれば,緑地帯による生物の生息地相互の連絡機能を兼ねた歩道・自転車道およびそのネットワークのことであり,本来的に多機能重合型(複数の異なる機能が1つの空間に重なっている)のグリーンインフラである.緑道は,1)健康寿命延伸への対応,2)交通安全対策,3)低密度な運動・移動環境の創出,4)中心市街地活性化,5)水循環系の修復,6)暑熱環境緩和,7)生物多様性保全といった諸問題を解決するブレークスルーとなる可能性を内包していると考えられる.本研究は,現存する市街地の高木街路樹に焦点を絞り,流動人口ビッグデータを用いて人の移動経路を可視化し,市街地の高木街路樹が人の移動に与える影響の解明を挑戦した.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
洪水常襲地帯に見る水防建築と浮体構法に関する研究
- 研究者名
- 畔柳 昭雄
- 所属組織
- 日本大学 理工学部 海洋建築工学科 特任教授
- 助成金額
- 120万円
概要
河川伝統技術としての水防建築は35 河川流域に見られ、その内18河川を調査対象としてきた。水防建築は治水整備の普及と生活様式の近代化により消滅の途に曝されており個人所有のため、維持管理が難しく改築・解体・放置が進む一方で、保存は極めて少なく記録収集は皆無に等しい。防水建築は減勢治水的思考に基づく減災的対応が建築的に図られることで浸水から距離を保つことを旨としていたが、地域的に「可動性」「可変性」及び「移動性」を備えているものも見られた。今回「移動性=(浮く)」に終点を絞り調査することにより、3 地域で見出すことができた。その実態を捉えるための現地調査を2ヶ所で実施した(コロナ禍で内1ヶ所は未踏査となり現在継続中)。今回捉えた浮く構法は洪水常襲地帯において流域固有の洪水特性や地域性など自然環境条件を反映することで考案され、風土的な地域的建築様式や建築に対する住み手の思考の差異などに基づき建築空間的な構成が図られていることを考究した。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
二段階横断方式における歩行者の心的負担を軽減する交通島の設計手法
- 研究者名
- 鈴木 一史
- 所属組織
- 群馬工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授
- 助成金額
- 120万円
概要
本研究では,わが国で導入事例が少ない二段階横断方式における交通島について,その望ましい設計手法を歩行者の心的負担軽減の観点から検討した.具体的にはVirtual Reality を用いて交通島を有する二段階横断方式を仮想空間内に再現し被験者に横断してもらうことで,交通島の構造条件(幅や形状,防護設備の有無等)が歩行者の横断挙動や交通島滞留時の心的負担に及ぼす影響要因を分析した.また,これら知見に基づき,大型車混入率や交通量等の道路交通条件に応じて,横断者の不安感を低減させる交通島の設計要件に関する知見を得るためのケーススタディを行った.その結果,二段階横断施設の設置対象となる道路の交通条件等に応じて,交通島の設計条件を変更した際の横断者の不安感が予測可能になるとともに,不安感を一定レベルに抑制するために必要な交通島の設計条件の検討に際して有用な知見を得ることができた.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
近代鎌倉長谷における老舗三橋旅館を介した地域交流に関する研究
- 研究者名
- 押田 佳子
- 所属組織
- 日本大学 理工学部 准教授
- 助成金額
- 86万円
概要
少なくとも19世紀以前より鎌倉長谷に存在した老舗旅館「三橋旅館」は、関東大震災による甚大な被災に伴い閉業した。その後、約100年間に亘り三橋旅館についての詳細は不明とされてきたが、この度、宿主後継者の協力の下、当時の資料を貸借、拝見することが叶った。そこで、これに基づく資料調査、ヒアリング調査をもとに、三橋旅館を中心に長谷で展開された地域間ネットワークを「地域交流状況」として明らかにしたうえで,近代長谷の発展プロセスを把握した。その結果、三橋旅館は海水浴場開設期以降、旅館経営を拡大しつつ、長谷の近代化を牽引したことを捉えた。一方で、三橋旅館に端を発する別荘地化の進展は、三橋旅館自体の衰退を招き、最終的には別荘文化とともに関東大震災で終焉を迎えたことが明らかとなった。その後、地域との関りが途絶えたとともに、三橋家所有の敷地も震災後の復旧事業や世代交代とともに縮小し、現状に至ったことが示された。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
海面処分場における安全で信頼性の高い遮水工構造の提案に関する研究
- 研究者名
- 稲積 真哉
- 所属組織
- 芝浦工業大学 工学部土木工学科 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
海面廃棄物最終処分場の環境安全性を建設段階から将来にわたって維持・保障した上で跡地利用を促すためには,水溶性廃棄物を含む保有水等の浸出を防止するとともに,廃棄物を効果的に浄化するシステムを構築することが重要である。
本研究は,H-H 継手の内部空間に種々の技術を適用した集排水機能を有する鋼管矢板部材を提案し,その実現性ならびに継手箇所における集排水特性を空間活用実証試験により追究する。その結果として,集排水機能を有する鋼管矢板部材としてH-H 継手の内部空間を活用した諸技術は導入可能であること,また,接着・塗布する膨潤性止水材の厚さを調整することでH-H 継手のフラン ジ嵌合部における遮水性能(集排水特性)をコントロールできることが明らかとなった。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
在日イスラム系外国人の避難所としてのモスクの利用可能性の検討
- 研究者名
- 小谷 仁務
- 所属組織
- 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 国際協力学専攻 助教(京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 助教)
- 助成金額
- 105万円
概要
外国人は宗教や文化の違いから災害時に被災弱者になりやすい.日本においては,特に,マイノリティであるムスリム外国人が避難所で食事や宗教的慣習の点で困難を抱える傾向がある.そこで,本研究では,在日イスラム系外国人が日頃から利用する礼拝所である「モスク」を彼ら・彼女らの災害時の自主的な避難所として利用することを提案し,避難所として機能するポテンシャルの評価を試みることを目的とした.モスクには礼拝スペースを含む広い空間があり,週末の礼拝後には利用者に食事が提供されることもあり,彼ら・彼女らが普段口にする食料が存在すると考えられたためである.本研究では,群馬県伊勢崎市の二つのモスクを対象に調査を行い,モスクの基本情報や設備,建物環境,避難者の収容可能人数,食材の買い置き量,管理者の協力可能性を調査した.結果,多くの避難者の一時的な滞在・宿泊可能な施設として機能する可能性が示唆された.本研究は,今後,モスクの避難所利用を精緻に検討していくための基礎的知見となる.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
災害時燃えずに電力を供給し生命を守る蓄電池の開発
- 研究者名
- 平郡 諭
- 所属組織
- 大阪工業大学 工学部環境工学科 特任准教授(大阪工業大学 工学部環境工学科 准教授)
- 助成金額
- 150万円
概要
現在定置型、及び移動型の蓄電池として最も用いられているのはレアメタルであるリチウムを用いたリチウムイオン二次電池である。小型・大型蓄電池に求められる要素は、高エネルギー密度、安全性、低コストであり、ポストリチウム二次電池にはこれらの特性を凌駕することが求められる。加えてリチウム資源は8割以上が南米に偏在しておりその価格は南米各国の経済状況に大きく依存するため安定していない。平常時のみならず災害時にこそ人々の生命と財産を守るためには安価で安全なポストリチウムイオン電池の開発が急務であることは言うまでもない。
申請者は現行の電池系では到達しえないような高い性能を達成しえる可能性があるだけでなく、安価で緊急時にも安心して使用できるマグネシウムイオン電池に着目し研究を行った。
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。