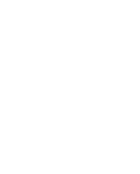検索結果一覧
65件中31件目から40件目を表示しています
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
鋼構造床版としてのマッシブ・ホルツ型木質パネルの鋼製床梁との接合に関する研究
- 研究者名
- 中島 史郎
- 所属組織
- 宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授
- 助成金額
- 126万円
概要
端柄材(製材の挽き板)を釘接合、または、ビス接合により積層成形したマッシッブ・ホルツ型木質パネル(以下、「木質積層パネル」と呼ぶ)を鉄骨造の梁に接合する際に用いる接合としてラグスクリュー接合を対象として、接合部の一面せん断試験を行った。また、同接合部の接合耐力(降伏耐力)と剛性を計算により求める方法について検討し、木質積層パネルの接合部に対する設計法について検討した。一連の研究により、接合部の降伏耐力については、接合部の仕様によって差違はあるものの、計算値は実験値と概ね近い値に求まっており、降伏耐力を概ね推定することができることを確認した。一方、接合部の剛性については、計算値が実験値よりも高く求まり、約2 倍となる仕様もあった。ラグスクリュー接合部のあそびによる剛性低下がその要因の一つと考えられるが、今後、精査する必要がある。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
鉄筋コンクリート造柱梁接合部の鋼板補強工法の実用化に関する研究
- 研究者名
- 上原 修一
- 所属組織
- 久留米工業大学 建築設備工学科 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
柱梁接合部の鋼板補強工法の実用化を目指し、そのディテールを確立するほか,有効性を実験的に示すことを目的として,試験体3体による実験的研究を計画した。試験体No.1は基準試験体,試験体No.2は鋼板を配置したもの,試験体No.3は試験体No.2に加えて梁主筋を直交鋼板に定着したものとした。実験上のトラブルで試験体No.2の結果が得られなかったが,試験体No.1と試験体No.3の結果より次の成果を得た。(1)施工上、問題のない鋼板形状,配置を提案できた 。 2) コンクリート強度が設計より大きくなり、鋼板の補強効果が十分に示せなかったが, 基準試験体と比較し, 試験体No.3では ,層間変形角 R =3.0 2 回目の加力で, 等価粘性減衰定数が 2 %程度増大 増大率は 17% することが明らかになった。
今後,梁主筋定着の効果を確認するため,追加の実験が必要である。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
都市農村交流による農村建築および周辺環境の再生を通じた都市機能不全時の生活基盤の継続的構築
- 研究者名
- 塚本 由晴
- 所属組織
- 東京工業大学 環境・社会理工学院 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、自給自足した里山の暮らしという伝統的な農村の再生を、気候変動下の都市インフラの限界に対するひとつの解決策と位置づけ、平常時の交流が都市機能不全時の予備生活基盤を形成するモデルを提示することを目的とした。農村住民によって里山環境を維持管理するために行われている「ちょこっと仕事」は、朝・夕に少しずつ行われることが多く、都市住民からは見えづらい。こうした「ちょこっと仕事」の集積が里山の風景を作り上げているのだが、高齢化のため集落内のメンバーではまかない切れなくなっている。一方、資源に触れ、時には格闘する「ちょこっと仕事」に、都市住民は非日常的な「遊び」やレジャーの要素を見いだすことができるはずだ。「ちょこっと仕事」を含む里山仕事を見える化することで、都市住民は普段から里山環境の維持管理に参加し、生活基盤を広げる手がかりをつくることができる。また、農業以外の里山利用と新しいメンバーシップを生み出すものとして森のようちえんに着目し、先行事例調査を行った。「ちょこっと仕事」と森のようちえんはともに身体が資源に向き合うふるまいであり、「ちょこっと仕事」は里山の再生につながる大人の利他的レジャー、森のようちえんは子どもの仕事である遊びであり、それらは農村住民と都市住民がともに里山の維持・利用をしていく次世代の都市農村交流をつくる。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
イギリスの都市計画プランナーの職能団体による実務研修等を支えるシステムに関する研究
- 研究者名
- 有田 智一
- 所属組織
- 筑波大学 システム情報系社会工学域 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では、イギリスの都市計画プランナーの職能及び職能団体による実務研修等を支えるシステムに関する研究を実施する。イギリスの都市計画分野に係る職能団体として、Royal Town Planning Institute(RTPI)を主な調査対象とし、1)実務経験審査手続き、2)継続的職能開発(Continuing Professional Development :CPD)の仕組み、及び3)専門家倫理、の3点について調査を実施した。調査の結果、今後の日本への示唆として、専門家に求められる資質―コンピテンシーが定義されていて実務研修のあり方について各自が研修内容をコアコンピテンシーとの関係で省察しながら構造化することを促す文書記録の仕組みがあること、研修プロセスをサポートするメンターを配置する配慮がなされていること、一連のプロセスを通じて自己啓発の継続による専門家倫理を自覚する機能があること、それらを客観的に第三者から検証可能な形での記録化を行う仕組みとなっていること等を指摘できる。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
初期反応性を高めた高炉スラグ固化体の創製
- 研究者名
- 胡桃澤 清文
- 所属組織
- 北海道大学大学院 工学研究院 准教授
- 助成金額
- 120万円
概要
本研究では、高炉スラグ微粉末と水酸化カルシウムを用いて高炉スラグ固化体を作製する。高炉スラグと水酸化カルシウムの割合を変化させて硬化に必要な最小量の水酸化カルシウム量をまず明らかにする。さらに加える水の量も変化させてそれが物性に及ぼす影響を明らかにする。上述の点を明らかにした上で初期強度発現の改善を行う混和剤の検討を行う。一方で、硬化体の微視的な評価を行うために結合水量、X線回折リートベルト解析による生成物の同定・定量化、水銀圧入法による空隙量測定、固体核磁気共鳴装置によるシリカ及びアルミニウムの結合状態測定を行った。最終的には製造した固化体の乾燥収縮量を測定するために乾燥収縮試験を行った。この結果より収縮量の少ない高炉スラグ固化体の製造方法の提案を行うことができた。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
RC造建物に導入する非線形TMDの普及に向けた新たな制振設計アプローチ
- 研究者名
- 金子 健作
- 所属組織
- 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 助教(東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 特任准教授)
- 助成金額
- 120万円
概要
耐震性の不足する鉄筋コンクリート造(RC造)を対象に,低コストな制振改修を可能とする線形・非線形TMDに対する制振設計法を構築した。はじめに,線形TMDに対して,非線形応答する建物への最適な剛性調整手法を定式化した。この手法をもとに,TMDの最大変形と建物の変位応答低減効果を関係づける制振性能曲線図を提示した。この図から,必要な制振性能とTMDの変形制限に対して,TMDの合理的な質量や減衰係数を視覚的に定めることができる。5階から14階建てまでのRC造共同住宅の立体振動解析を実施し,中小〜大地震を想定した観測地震動に対して,15〜20%の変位応答低減効果を確認した。さらに,線形TMDの減衰機構を摩擦機構に置き換えた非線形TMDを提案し,RC造に適用した場合の制振設計を支援するツールを整備した。このツールは,多数の非線形時刻歴応答解析を学習した深層ニューラルネットワークをソルバーに有し,ユーザーが対話的にTMDの諸元を変えることにより,制振性能を視覚的に評価できる。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
都市公園としてのプレイパークの横断的調査研究-利用者と運営者視点より
- 研究者名
- 早川 礎子
- 所属組織
- 小田原短期大学 通信教育課程 特任教授(山村学園短期大学 専任講師)
- 助成金額
- 118.4万円
概要
都市公園を見れば、その地域の印象が見えてくる。公園は憩いの場であり、親子の遊びの場でもありながら、街の景観の一つであり、その地域の文化や美意識を反映している場所でもある。また子育て支援機能を有しており、広場や遊具等の整備等により、その機能を保持してきた。
本研究は、全国に展開している都市公園におけるプレイパーク(「プレーパーク」「冒険遊び場」とも示される)を特定の地域に限らず東京のベットタウンである埼玉県、千葉県、神奈川県を横断的に研究の対象とした。子どもたちの身近な遊び場の必要性について横断的な方法で質問紙調査(①利用者向け、②運営者向け)を行った。また感染症対策を講じた上での観察調査を行った。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
深層学習を用いた被害写真に基づく震災マンションの早期復旧支援ツールの開発
- 研究者名
- 吉岡 智和
- 所属組織
- 九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授
- 助成金額
- 120万円
概要
大地震で被災した共同住宅の早期復旧支援のため,専門家に代わり架構の地震応答を推測するAI の開発の一環として,畳込みニューラルネットワークモデルを用いた深層学習により生成した識別器によりRC 方立壁の被害写真から損傷度を判別し,その損傷度からRC 方立壁が経験した最大変形角を予測する手法を提案した。提案した予測法の妥当性を検討するため,実大RC 方立壁の水平加力実験を行い経験変形角毎の壁面の損傷写真を収集し,比較検証を行った。その結果,収集した損傷写真を用い提案した予測法により,RC 方立壁の損傷度,及び変形角を推測したところ,実験結果を概ね評価できることを確認した。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
首都圏郊外における軍事基地周辺の都市空間形成
- 研究者名
- 塚田 修一
- 所属組織
- 中央大学 文学部 兼任講師(相模女子大学学芸学部講師)
- 助成金額
- 54万円
概要
本研究は、首都圏の在日米軍および旧日本軍の軍事基地、および自衛隊基地が所在する(していた)地域を対象とし、そこがどのような空間形成過程を辿り、どのような景観が形成されているのかを明らかにしていく。具体的には、神奈川県横須賀市、埼玉県所沢市、千葉県松戸市、東京都北区を調査する。研究方法として、地域の市史や都市計画資料といった史資料による、空間形成過程の調査(通時的考察)と、都市景観の現状のフィールド調査(共時的考察)の二方向の調査を接続させることで、軍事基地を抱えた都市空間の歴史と現在を立体的に把握、描出する。
上述の研究対象・方法に基づき、本研究では、前期・中期・後期の三期間に分けて調査・分析を進める。前期は各地域の図書館、国会図書館で文献資料の収集・分析を行い、都市空間形成の過程を明らかにする。中期では前期の調査を踏まえ、各地域の実地調査によって、都市景観や空間利用の現状を明らかにする。後期は各地域における通時的考察と共時的考察を統合し、対象を立体的に把握する。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
都市整備にあたっての多様性の効果に関する研究
- 研究者名
- 中村 隆司
- 所属組織
- 東京都市大学 工学部都市工学科 准教授
- 助成金額
- 112.8万円
概要
都市整備における多様性の必要性は国際的に共通の認識になってきているが、多様性が具体的にどのような効果をもたらすかについては、明確で無い。申請者がこれまで行って来た研究からは、駅乗降客数と周辺土地利用、多様な住宅形態の存在等と高齢化、③多様な機能の集積と中心市街地の人口や従業者の維持には関連がうかがわれるが、これらの点については、さらなる調査が必要である。そこで、本研究は、多様性をエントロピー値に数値化すること等を通じて、A 駅乗降客数への効果、B 高齢者の集中への影響、C 地方都市中心市街地における人口と従業者の維持との関係、D 東京一極集中の中での地方中枢中核都市の活性化方策について、今後の都市整備にあたっての多様性の効果と必要性を明確にするものである。
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。