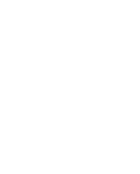検索結果一覧
65件中41件目から50件目を表示しています
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
多様な空間データの融合による望ましい土地利用の将来像の解明の研究
- 研究者名
- 嚴 先鏞
- 所属組織
- 東京大学 空間情報科学研究センター 特任研究員
- 助成金額
- 96万円
概要
多様化している人々の住環境に対するニーズにこたえながら,人口減少,環境問題に対応できる地区レベルの土地利用の将来像を明らかにすることを目的し,(1)多様なデータの融合による土地利用パターンの定量化手法を開発し,(2)ビックデータに基づいた多様なニーズを考慮した土地利用パターンを住宅の価額と人出の変化から明らかにする.さらに,(3)望ましい土地利用の実現のための誘導の方策について検討することを通して,多様な用途が調和したコンパクトな市街地形成に寄与することが期待される.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
広域ネットワークとしての沖縄・台湾製糖施設の歴史的評価と効果的な活用方法
- 研究者名
- 西川 博美
- 所属組織
- 岡山県立大学 デザイン学部 デザイン工学科 建築・都市デザイン領域 准教授
- 助成金額
- 98万円
概要
沖縄・台湾における製糖産業施設として、製糖工場の建設について主に史料から明らかにした。台湾においては、台湾総督府による製糖業振興と内地からの製糖業への資本投下により、台湾南部を中心に数多くの大規模製糖工場が建設された。沖縄でも、台湾に倣い白糖(分蜜糖)の生産に取り組むようになり、大規模な工場が建設された。しかし、台湾では総督府の指導のもとに、半ば強制的にではあるが独自の区域制度を設けることで、収穫したサトウキビは全量を契約した製糖会社におさめる仕組みができていたため、工場と周囲の農地に強固な関係が築かれ、それが私設鉄道のネットワークも生み出した。それに対して、沖縄では工場と農地にそうした関係が築かれなかったため、工場の生産性に限界を迎えることとなったことが指摘されている。大規模な工場遺産をどのように価値付けるかについては、施設と周囲の関係を捉えることが重要であることが改めて認識された。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
地割単位で連結した旧街道町の駐車場周辺の温熱環境改善を目的とした樹木ユニットの開発
- 研究者名
- 髙田 眞人
- 所属組織
- 熊本大学 工学部 土木建築学科 建築学教育プログラム 助教
- 助成金額
- 120万円
概要
申請者は,熊本市内の旧街道町(京町地区)において,伝統的な地割単位で造成された駐車場が連結して巨大なアスファルト面を形成し,そこに地域の上空風が誘引されることで,夏季に周囲の温熱環境を悪化していることを過去の実測調査より明らかにした.本研究課題は,舗装された駅前空間の土地被覆を仮設的な緑地で改変することで周囲を含めて良好な温熱環境の形成が可能という既往研究を参考に,駐車場に設置可能なコンテナ型樹木ユニットの開発を目的とする.また同時に,地域の伝統的な地割を活かし環境に配慮した建築と街並み設計への知見も得ることも目指した.
本課題はコロナ蔓延を受け期間の延長が認められ,計2 年間実施された.1年目(2020.4-2021.3)は樹木ユニットの開発とユニット単体及び組み合わせによる環境改善効果を検討した.続く2 年目(2021.4-2022.3)は駐車場設置型の緑化パークレットの提案を研究目的に新たに加え,樹木ユニットを改良するとともに熊本市内の商店街において社会実験を実施し,歩道も含めた総合的な都市緑化方法について検討した.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
都市のリスクに対応した次世代居住環境モデルの研究―水害・高齢化リスクを考慮した、地域の豊かな関係性をもたらすアムステルダムの居住環境からの示唆―
- 研究者名
- 寺田 真理子
- 所属組織
- 横浜国立大学 都市イノベーション研究院 "Y-GSA" 准教授
- 助成金額
- 120万円
概要
本研究は、⾼齢化や⼈⼝減少、都⼼住宅の⾼騰化によってもたらされる⼈々の孤独や孤⽴といった、都市のリスク/社会的課題に対応した「次世代居住環境モデル」のあり⽅を提案することを⽬的としている。⽇本と社会課題が類似するオランダの都市開発における集合住宅の歴史を辿り、時代ごとの社会的背景と開発主体の規模や住宅の供給⽅法の変遷において、集合住宅の居住空間における「公 / 共 / 私」の空間構成にどのように影響を及ぼしてきたのか、その相関関係を調査した。今や住宅を中⼼とする都市や地域の開発には⾏政主導型のトップダウン⽅式や⺠間企業主導だけのものでは社会の要求に対応できなくなっている。オランダのCPO やコーポラティブの仕組みなどを利⽤した住⺠主導のボトムアップ⽅式の住環境づくりは、居住者同⼠、近隣住⺠とのつながりを⽣み出す可能性が⾼く、住⺠が主体的にそれに関わることで共的空間のあり⽅が変化し、社会課題に対応したレジリエントなコミュニティや居住環境の構築につながっていることが確認できた。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
視覚障害者の鉄道駅のプラットホームからの転落を防ぐための対策
- 研究者名
- 徳田 克己
- 所属組織
- 筑波大学 医学医療系 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、視覚障害者の転落経験を詳細に聞き取り、ホーム上にどのような課題があるのかを整理した(研究1)上で、実際のホームにおいて具体的にどのような問題があるのかを明らかにしたい(研究2)。本研究の結果、視覚障害者がホームから転落する原因として、転落防止幌の問題、点字ブロックの問題、ホーム上の空間構成の問題、転落防止柵やホームドアの問題、手引き者の技術不足などが確認された。その中で、ホーム端に内方線付警告ブロックが設置されている駅と内方線のない警告ブロックが設置されている駅が混在している、島状のホームの一端はホーム柵が設置されているにもかかわらずその反対側は設置されていないなど、さまざまな点で統一されていない問題が明らかになった。また、ホーム上を直進するための連続した手がかりがないことも問題であった。これらのことから、ホームドアの設置は望まれるが、その前に不統一の箇所を統一すること、ホーム上には移動すべき方向が確実にわかる手がかりが連続的に確保されることが必要である。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
都市の特性に応じた事前災害対策と復興政策の検討に向けた回復モデルの構築
- 研究者名
- 塩崎 由人
- 所属組織
- 金沢大学大学院 自然科学研究科 特任助教(防災科学技術研究所 災害過程研究部門 特別研究員)
- 助成金額
- 124万円
概要
我が国は、大規模災害によって都市が大きな被害を受ける可能性がある。災害によって引き起こされる人口流出や産業への被害を契機に、それまで存続していた都市が、被災した状態から回復できず、衰退する等、望ましくない状態に陥る可能性も指摘される。本研究では、被災した都市の状態の動的変化を表現可能な数理モデルを構築し、その特性に応じて都市が被災した場合に陥る可能性がある状態のパターンとメカニズムを明らかにした。その上で、都市の特性に基づき、講じるべき対策の方向性を検討した。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
用途廃止をした公共施設の公共的暫定利用に関する研究研
- 研究者名
- 小松 尚
- 所属組織
- 名古屋大学大学院 環境学研究科 都市環境学専攻 建築学系 教授
- 助成金額
- 127万円
概要
フランス・パリのLesGrandsVoisinsプロジェクト(以下LGV)は廃病院の建物や屋外空間を2015年から2020年9月まで、多民族、多業種、多目的の市民が共存できる公共空間として暫定的に利用された。その成果を跡地の再開発計画等へフィードバックする目的を持った暫定利用であった点に特徴があり、またわが国の既存建築の有効利用に大きな示唆を与える可能性がある。そこで本研究は、廃病院跡地の暫定利用のプロジェクトでありながら、跡地や周辺の再開発と連動して行われ、多様な市民のための公共空間としてフランス国内でも評価されているLGVの運営、プログラム、空間、そして再開発計画との連動性について分析、考察する。
なお、新型コロナウイルスの世界的感染拡大により、フランスの事例を対象にする現地調査等、研究が遂行できなくなったため、研究助成期間の延長を2度承認いただき、2023年3月まで実施し、本研究課題に関連する国内事例の研究を追加して行った。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 建築技術
データ駆動型の建築構造力学の基盤技術の創出
- 研究者名
- 寒野 善博
- 所属組織
- 東京大学 数理・情報教育研究センター 教授
- 助成金額
- 100万円
概要
データ駆動型の方法論は,近年,理工学のさまざまな分野で急速に展開されてきている.この状況を受けて,本研究課題では,建築構造力学における最も基本的な問題として弾性構造物の静的な釣合い解析をとりあげ,材料実験のデータを直接的に利用する手法を開発することを目標とした.従来の釣合い解析では,材料の構成則を実験結果から経験的にモデル化する必要がある.これに対して,ここで開発したデータ駆動型の手法では,モデル化を経ることなく材料実験のデータを利用して構造物の釣合い解析を行うことができる.このため,構成則のパラメータのキャリブレーションなどが一切不要である.この提案手法は,材料実験のデータ点が応力・ひずみ空間のある多様体(曲面)上に分布するとみなせることに着目しており,その多様体を表す方程式を予測するという手法で構成されている.本研究課題では,計算機実験により提案手法の有効性を確認した.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
SDGsとCPTEDアプローチによるメキシコ・スラム集住地の住環境イノベーションに関する研究 -IDA手法の適用と教育モデル検証-
- 研究者名
- 郭 東潤
- 所属組織
- 千葉大学大学院 工学研究院 助教
- 助成金額
- 150万円
概要
現在のメキシコは総人口約1億3千万人のうち、約80%が都市部に居住していると推計されている。こうした圧倒的な都市人口率の高さは、不均質な開発と貧困の拡大を引き起こす原因でもある。都市部の貧困層は経済的または社会的に排除され、その結果としてインフォーマルな方法や土地の違法な占拠、自助建設によって住居を獲得し、スラム集住地を形成し拡大している。これによって住環境の悪化がますます懸念されている。本研究ではメキシコ・ハラパ市のスラム集住地を対象に、スラム集住地の環境的特性に関する調査と、CPTEDの観点からの住民アンケート調査を行い、住民の「LocalSafety」に関する住民意識構造を分析した。
(補注:新型コロナウィルス感染の影響により、申請時に予定されていたInteractiveDesignArchitects(IDA)手法を適用することができなかった。)
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
千葉県に残る特異な形態の本堂内宮殿(厨子)に関する建築史的研究
- 研究者名
- 上野 勝久
- 所属組織
- 東京藝術大学 美術研究科 教授(東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻)
- 助成金額
- 150万円
概要
大山寺は、千葉県鴨川市に所在する真言宗寺院である。
大山寺不動堂は、令和2年度の調査により元禄12年(1699)と推測できる箇所が確認でき、宮殿の建築年代を元禄12年とする確立は極めて高いと考えられる。
大山寺宮殿は、不動堂の建立年代の享和2年よりもはやい建立年代が明らかとなった。これは、不動堂の前身堂(天正14年(1586)建立(「大山寺不動堂棟札」(個人蔵)より))に現在の宮殿が建設された後、現在の不動堂(享和2年)が、覆屋のように建設されたと推定している。
また、宮殿のみで建築形態が完結している点からも、前身の仏堂の一部を再利用してつくられたという通常と異なる形成過程の可能性が理解できる。つまり、壮大な宮殿を包み込む覆屋のように、現在の不動堂が建設されたと考えられる。
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。