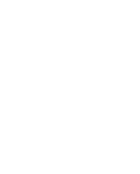検索結果一覧
65件中51件目から60件目を表示しています
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
「動的」ヒートアイランドへのパラダイムシフトと新指標の構築
- 研究者名
- 本條 毅
- 所属組織
- 千葉大学大学院 園芸学研究科 教授(千葉大学大学院 園芸学研究院)
- 助成金額
- 150万円
概要
従来のヒートアイランド研究では、ヒートアイランドは静的なものとして捉えられていた。しかし、関東地方のような沿岸部の都市では海陸風の影響で、ヒートアイランドの分布や形状は1日のうち時間とともに大きく動的に変化し、また、季節的にも変化する。そこで、本研究では関東地方のヒートアイランドの分布が、どのように1日あるいは季節で変化するかを、ヒートアイランド偏差、ヒートアイランド中心などの指標を用いて解析した。とくに、長期間の関東地方のヒートアイランドの変化を見るため、過去40年のAMeDASのデータを用いて、経年的にどのように変化したかについて解析した。その結果、平均気温は上昇しているものの、ヒートアイランドの動的パターンは、あまり変化していないなどの興味深い結果が得られた。
世界的には、静的ヒートアイランドの概念がまだ一般的ではあるが、本研究ではヒートアイランドが動的であることや、指標としてヒートアイランド中心を用いることの有用性を示すことができた。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
低平地に位置する歴史的地方都市における複合災害を考慮した高所避難に関する研究
- 研究者名
- 三島 伸雄
- 所属組織
- 佐賀大学 理工学部 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
近年増加している自然災害、ならびに2018年の農業用ため池の決壊に対する懸念が増加して緊急対応としての避難計画が求められている。そこで、特に低平地に位置して避難所周辺に狭隘道路や坂道の多い歴史的地方都市を対象として、避難所への再避難や要援護者へのケア不足による二次災害を含む複合災害を考慮して、避難者トリアージの有無を比較する避難シミュレーションを行なった。その結果、避難者トリアージで要援護者を最適な避難所に誘導することによって、再避難等をなくすことができ、高所避難の時間を短縮できることを明らかにすることができた。以上より、避難者トリアージの有効性を示すことができた。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
現代社会において移動困難者が感じている新しい都市バリアの解明
- 研究者名
- 水野 智美
- 所属組織
- 筑波大学 医学医療系 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、歩きスマホ、迷惑ランナー、キャリーケースの牽引、エスカレータの駆け上がり、駆け下りといった都市バリアの現状と一般成人の認識を明らかにするとともに、視覚障害者、高齢者、乳幼児を持つ保護者、肢体不自由者といった移動困難者が都市バリアについてどのような問題やトラブルを抱えているのか、どういったニーズをもっているのかを明らかにした。さらに、これらの都市バリアに条例の制定がどの程度の効果があるのかを確認するために、墨田区で施行された歩きスマホ条例の施行前後で歩きスマホ者の割合の変化を測定した。
一般成人は歩きスマホ等によって自分がトラブルに巻き込まれることは迷惑に感じていながらも、他者、特に移動困難者をトラブルに巻き込んでいることを十分に意識しておらず、自身の行為をやめられない現状があった。条例を制定するだけでは、都市バリアの解決には至らず、これらの行為が他者にどのような問題をもたらすのかを具体的に啓発する必要性が示唆された。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
資源循環形成に向けた下水汚泥の新規無害化手法の開発
- 研究者名
- 伊藤 歩
- 所属組織
- 岩手大学 理工学部 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では,バイオガスを回収した後の下水消化汚泥をより安全・安心な肥料原料として循環利用できるように汚泥中の有害物質(重金属類と抗菌性物質)の除去手法の開発を試みた.まず,硫酸で汚泥を酸性化して汚泥固相の重金属類を溶出し,その重金属イオンをメッシュバッグに封入した固形状キレート剤で吸着回収する方法を検討した.pHを2に調整した汚泥に固体状キレート剤を添加してpHを3~4に再調整することでNiとFeの40%前後,PbとCdの50~60%,Znの90%をメッシュバッグとともに除去回収できた.次に,酸性化した汚泥に鉄(VI)酸カリウムを添加することで汚泥中のシプロフロキサシン,アジスロマイシン,オキシテトラサイクリン,テトラサイクリンの濃度を半分以下に低減でき,汚泥中のリンを沈殿させることができた.これらの知見は資源循環形成に向けた下水汚泥の新規無害化手法を開発するうえで有用である.
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
フィリピン・マニラ首都圏における統合的利水管理プラットフォームの構築
- 研究者名
- 矢澤 大志
- 所属組織
- 立命館大学 理工学部 助教
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は,近年”Water crisis”と言われる程の水不足を経験したフィリピンでSoil and Water Assessment Tool(SWAT)を適用して分布型流域統合モデルを構築し,流出解析を行うことを目的とする。現在首都圏への約97%の水を供給しているAngat-Ipo-La Mesa Water Systemを構成している主要河川(アンガット川),および今後の水供給源として期待される河川(パンパンガ川とアゴス川)を対象とし,河川流域内の河川流量を水供給(可能)量として計算した。
対象流域において河川流量の計算や土地利用シミュレーションを行うことにより,森林の存在が一定の水源涵養機能を持ち,特に雨季の洪水に対して効果があるが,乾季の渇水に対してはあまり効果がないことが分かった。そのため,マニラ首都圏への水源確保のためにはダム建設などハード面での整備も継続する必要がある。一方,本研究の計画では現地調査を行うことでデータ収集や水需要量の調査を予定していたが,昨今の状況に鑑み延期せざるを得ない状況となった。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
大規模小売店の閉店が地域内購買活動に与える影響に関する実証
- 研究者名
- 宮内 悠平
- 所属組織
- Boston University, Department of Economics, Assistant Professor
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では、大規模小売店の閉店が近隣地域の消費活動に与える影響を分析する。特に、消費者の消費移動行動をデータで把握するために、スマートフォンのアプリから収集された人口流動データ(日本人口の1%程度をカバー)を用いる。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
健康寿命延伸のための立ち座り動作の質的評価に着目した居住空間の健康増進レベル評価
- 研究者名
- 小川 愛実
- 所属組織
- 慶應義塾大学 理工学部 助教
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では日常生活動作の中でも特に下肢関節の負荷が大きく難易度が高いことで知られる立ち上がり動作を対象に、新しい評価手法の提案と環境変化による動作への影響の調査を行った。立ち上がり動作の評価には、時系列データの平均値やピーク値を用いることが一般的であるが、時間的要素が考慮されないという問題点がある。そこで本研究では、基本となる条件で取得した動作の時系列データを基準とし、他の条件のデータに動的時間伸縮法を適用させ基準動作からの逸脱度を表すことで、時系列を考慮した新たな評価指標を提案した。立ち上がり動作は日常生活中に多様な環境下で実施され、それぞれの環境要素の影響を受ける。環境要素には座面の高さや傾斜角度、硬さがあるが、高さの検証が多いのに対し傾斜角度や硬さに関する研究は少ない。そこで本研究では座面の傾斜角度および硬さが立ち上がり動作に与える影響の定量的評価を行った。本研究は居住空間の多様な環境に対する動作負荷ポテンシャルを示す新しい試みである。
- 2019年度(令和元年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
アクティブシニアの田園回帰がもたらす3世代移住の実態及び可能性
- 研究者名
- 新 雄太
- 所属組織
- 東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 特任助教
- 助成金額
- 146万円
概要
親世代の田園回帰により,子・孫世代が移住先地域と多様な縁を持つ現象に注目し,縁もゆかりも無かった土地にいかにして多世代が関係し,暮らしているのかを明らかにするために,全国規模のウェブアンケート調査を行なった。事前調査において,移住後20年以内で20〜79歳の3世代移住者は3.4%の出現率と推定された。これにより8,177件配布し,300件の標本を取得した。
3世代移住者は,両親世代と子世代を持つ回答者タイプが最も多く(63%),約2/3が家族や自身のライフステージの変化を移住理由として挙げた。ワークライフバランスについては、移住後に家庭生活を優先にする回答者が約15ポイント増加し,約1/3 仕事関係での繋がりを求めなくなった。過半数が家族内の自身の役割を理解し,3世代間の家族関係は移住後概ね好転している。幸福度,ソーシャルキャピタル,効力感ともに高く,特に若年層を起点する3世代移住は、「自己実現と他者への貢献感」や「自己受容と内面的成長」が有意に高い結果となった。
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
木造耐力壁の面内せん断性能における周辺部材の影響の検証
- 研究者名
- 中 太郎
- 所属組織
- 東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 木質材料学研究室
- 助成金額
- 80万円
概要
国内外において中大規模建築物の木造化の取組が急速に進展しているが、我が国において、中大規模木造建築物を対象とした体系的な構造設計指針は未だ整備されていない。本研究で取り上げる耐力壁構造建築物については、現在広く参照されている既往の設計指針では主に住宅規模の建物を対象としており、建物規模が増大した時の問題点が明らかでない。本研究では、耐力壁を用いる中大規模木造建築物を対象とし、耐力壁の性能に対して柱脚接合部や境界梁と言った周辺部材が与える影響を実験的・解析的に検証し、特に耐力壁柱脚接合部の保証設計法の構築を目指す。提案する保証設計法は、鉄骨造の露出型柱脚の設計フローや木造ラーメン構造のモーメント抵抗接合部の性能推定理論を参考にしながら、木造耐力壁構造に特有の浮き上がり現象を簡便に考慮できる新しい計算法であり、その妥当性を実験及び解析によって検証する。
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
台湾における2009年モロッコ台風災害後の住宅再建プロセスに関する調査研究
- 研究者名
- 蔡 松倫
- 所属組織
- 京都大学大学院 地球環境学舎 人間環境設計論分野
- 助成金額
- 75万円
概要
本研究は、2009年モロッコ台風による台湾南部山間地域の少数民族の災害復興住宅再建プロセスに着眼し、政府の再建政策、再建場所の選択、生業と文化に関する復興、各ステークホルダーの役割とプロセス参加度に基づき、台湾の災害復興プロセスについて総合的に分析した。研究対象は、台湾南部山間地域で被災した五つの少数民族集落である(Rinari, Ulaljuc, Xinlaiji, Changzhi, Jialan)。被災者、政府職員、NGO担当者に対するフィールド調査と災害復興に関する報道のテキスト分析により、災害復興プロセス各側面の時系列的な関係を明らかにした。本研究により、今後の災害再建フレームワークの改善について、新たな方向性が提示された。
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。