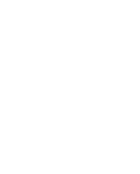検索結果一覧
65件中61件目から65件目を表示しています
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
都市計画の歴史社会学―civicの歴史的変遷に着目して
- 研究者名
- 中川 雄大
- 所属組織
- 東京大学大学院 学際情報学府 学際情報学専攻 文化・人間情報学コース 吉見俊哉研究室
- 助成金額
- 80万円
概要
本研究は、近代日本社会において都市計画を実施する上で、「都市計画を支える市民意識」=civic という価値がどのように構成されてきたのかを明らかにするものである。「シビックプライド」という言葉は現代のまちづくりでも注目されている。しかし、単なる都市の物理的な変化のみならず、住民の都市に対する責任感や自治、愛着という価値観(以下、本研究ではそれらを civicと称する)は 20 世紀に日本に都市計画が導入された当初から都市計画家が重視し、繰り返し住民に求めてきたものでもあった。 そこで 本研究は、 1920 年代と 1960 年代の 都市計画 や都市開発において、 civic という概念がいかに運用されてきたのか について 、都市計画を都市住民に伝えるメディアや区画整理におけるコミュニケーションに着目して 検討した。 そして、都市計画を推進した価値観がどのように人びとに影響を及ぼしてきたのか議論した。
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
木材の応力緩和の特性把握のための実験的研究
- 研究者名
- 中山 翔太
- 所属組織
- 東京大学大学院 農学生命科学研究科 木質材料学研究室(小西泰孝建築構造設計)
- 助成金額
- 80万円
概要
近年、鋼材との混構造や摩擦接合による耐震構造など、木材の摩擦力を利用した構造形式が選択されることが増えている。摩擦力の管理には、木材に生じている締め付け力の管理が重要となる。一方で、木材はセルロース・セミヘルロース及びリグニン等の高分子により構成されているので、粘弾性の性質を有する。つまり、摩擦力を利用した接合部で木材は変位一定で固定されているので、木材に生じている締め付け力は応力緩和により減少する。そのため、接合部に生じている摩擦力を評価するためには、木材の応力緩和を適切に評価する必要がある。本研究では、印加時間・余長・加力方向及び樹種が応力緩和に与える影響を検証し、木材に生じる応力緩和の基本的な性質の解明を目的とした。
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
高速道路斜面災害に対する通行規制基準の高度化
- 研究者名
- 橋詰 遼太
- 所属組織
- 大阪大学大学院 工学研究科 社会基盤マネジメント学領域
- 助成金額
- 64万円
概要
我が国の高速道路は全供用区間で10万か所以上の法面が存在し、降雨による斜面災害に対して十分な対策が求められる。斜面災害による道路利用者の被災を防止するため、降雨時には通行規制が実施されている。一定の雨量を超過した時点で通行規制が開始され、降雨終了から一定期間経過後に解除される。一方で、近年の集中豪雨や局所的豪雨の増加といった降雨傾向の変化に伴い、通行規制基準に達する前に斜面災害が発生する「見逃し」や、通行規制時間の増大が報告されている。本研究では、蓄積された降雨データ、差異が履歴データを用いて降雨中に発生する災害及び降雨終了後に発生する災害に対して予測モデルを作成する。それぞれの予測モデルの予測値に基づいた通行規制基準の設定によって、道路利用者の安全性確保と交通機能確保を両立できるような交通規制基準の策定を試みる。
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
スリランカにおける復興過程から見たレジリエントな減災地域社会の構築条件の解明
- 研究者名
- 土田 亮
- 所属組織
- 京都大学大学院 総合生存学館 寶研究室
- 助成金額
- 64万円
概要
本研究の目的は、スリランカで頻発し、被害規模が拡大しつつある洪水災害に対して、復興過程における生業と社会的環境、居住環境に着目しながら、レジリエントな減災地域社会を構築するための条件を明らかにすることである。本実施年度では新型コロナウイルスの影響により、現地調査を遂行することはできなかったが、その代替として調査対象地である1819年から1937年の記述が残っているスリランカ・ラトゥナプラ市の公文書をもとに分析した。文献を分析した結果、甚大な洪水災害が起きた1913 年当時、イギリス植民地時代の影響を色濃く受けた役職が活躍していたこと、かつてオランダ植民地だったときの建造物が避難場所として活用されていたこと、シンハラ社会における地縁関係や自然資源を活用した災害対応と復興がなされていたことが類推された。
- 2019年度(令和元年度)
- 奨励研究
- その他
木骨煉瓦造建造物の構法に関する日欧比較研究
- 研究者名
- 冨士本 学
- 所属組織
- 東京大学大学院 工学系研究科 腰原研究室(東京大学生産技術研究所)
- 助成金額
- 80万円
概要
申請者は、日本近代における西洋からの建築技術の移転のメカニズムを解明することを目的に、木骨煉瓦造建造物を対象として研究を行っている。木骨煉瓦造とは、木造軸組と煉瓦組積壁を組み合わせる構法である。幕末期に「お雇い外国人」として来日したフランス人技師によって導入され、横須賀製鉄所や富岡製糸場が建設された。その後、工場建築のほか、学校建築や住宅倉庫などにも用いられたが、複数の地震被害や他の構造技術の発達とともに用いられなくなった。国内の現存事例の多くが建設後100年以上経過しており、また地震に対し脆弱な構造であるため、保存・保全を行うには、歴史的な価値評価とそれに基づく耐震補強が必要不可欠である。本研究は、建造物の価値評価に必要な歴史的背景を明らかにするため、日仏間で木骨煉瓦造の現存事例や当時の資料を分析・比較することを通じて、その技術移転のプロセスについて考察するものである。
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。