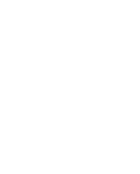検索結果一覧
821件中131件目から140件目を表示しています
- 2021年度(令和3年度)
- 奨励研究
- その他
瀬戸内海文化圏に立地する宇佐神社の歴史と空間分析から捉える重層的な地域圏の構築
- 研究者名
- 泉川 時
- 所属組織
- 早稲田大学大学院 創造理工学研究科 後藤春彦研究室(早稲田大学 創造理工学部建築学科 助手)
- 助成金額
- 79万円
概要
行政圏を超えた建築から都市・地域までスケールを媒介した文化圏を提示するため、瀬戸内海に立地する宇佐神宮を本宮とする宇佐神社の重層的な地域圏域を明らかにした。30社の宇佐神社からなる文化圏は、建築や環境の共通項が見出された。一方で、創建の年代や立地の類型化から東西の偏り等が認められず、各地で勧請する環境が整った時期に分霊したといえる。そのため、その後何百年もの間宇佐神社の信仰を継承しながらも、地域独自の民俗文化が生まれ、有形・無形の個別の地域資源が現存している。こうした歴史的な地域資源を総体として伝えやすい形に編集することで、小単位でのまちづくり活動に活かしつつ、これを総括する瀬戸内海文化圏のように大きな単位での計画を行うことで、地域の内外の人が持続的な地域づくりを行える環境を形成すべきだといえる。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) 瀬戸内海文化圏に立地する宇佐神社の歴史と空間分析から捉える 重層的...
- 2021年度(令和3年度)
- 奨励研究
- その他
ウォーカブル政策と実行計画に関する日・英の比較研究
- 研究者名
- 井桁 由貴
- 所属組織
- 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 社会文化環境学専攻 空間計画研究室
- 助成金額
- 80万円
概要
本研究は、①日本のウォーカブル施策の特色を明らかにすること、②ウォーカブル施策において先進的な英国との比較から、わが国のウォーカブル政策に対して示唆を与えることの二点を目的とした。具体的には、国内及び英国のウォーカブル政策・実行計画に関する時系列的な変遷を整理した上で、富山市と英国ロンドンにて現地調査・ヒアリング調査を行った。結果として、ウォーカブル政策の背景、実行プロセス、政策と実行計画に関して日・英の違いが明らかとなり、日本におけるウォーカブル政策の方向性が示された。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) ウォーカブル政策と実行計画に関する日・英の比較研究 研究者名※ 井桁 由貴...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
施設配置における民意と費用対効果との齟齬―インフラ維持負担増とデジタル化を踏まえて―
- 研究者名
- 大澤 義明
- 所属組織
- 筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
我が国では,少子高齢化の進行,働き方改革の浸透,感染症対策さらには運転者不足も相まって,減便など公共交通の見直しが進んでいる.バスサービスの変更では住民ら地域との合意形成が不可欠ではあるが,民意による判断は必ずしも合理的とはならない.本研究は,既存の一対比較施設配置モデルを拡張し,バス利用者からの運賃でバス運行費が調達される収支完結構造に機会費用を組み込んだモデルを構築する.そして,バス利用者の希望時刻に多様性がある場合に,住民要望などの民意がバス本数の過剰供給を導くこと,繰上コストの改善が民意と効率性との乖離を拡大させることのメカニズムと規模を理論化し,民意がバスサービスの合理化の障害となることを示す.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 施設配置における民意と費用対効果との齟齬―インフラ維持負担増 とデジタル化を...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
北前船寄港集落を形成する自然環境要因と地域の社会特性の研究
- 研究者名
- 南 一誠
- 所属組織
- 芝浦工業大学 理工学研究科 建設工学専攻 教授(建築学専攻兼務)
- 助成金額
- 135万円
概要
日本海側の地域には、北前船が運行した時代に発展した商港が今もその形を残している。海流、季節風、豪雪、河川、背後の山からの伏流水などの自然環境が集落形成の基礎となり、その地に相応しい建築構法が、地域の林業、農業、大工、職人らによる生産組織により成立していた。気象庁日本海海洋気象センターや各地方気象台の公開情報、日本地図センター発行の地図や海上保安庁の海流実況図などにより、集落の自然立地特性を分析した。集落の建築群としての集合形式については、実測や許可されたエリアでのドローンによる撮影を行い分析した。建築構法については、各地の民家の実態調査のほか、それらの修理を担っている工務店等へのヒアリングを行った。調査結果をもとに伝統集落、伝統建築に潜在する自然環境、地形と建築生産システムの複合的特性について分析し、地域に最適な持続可能な都市、建築の生産・整備手法を成立させていた要因の分析を行った。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 北前船寄港集落を形成する自然環境要因と地域の社会特性の研究 研究者名※ 南 一誠...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
原位置加熱浄化技術の開発に資する重金属類の吸着・脱離特性の温度依存性評価
- 研究者名
- 斎藤 健志
- 所属組織
- 埼玉大学 大学院理工学研究科 助教(国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 主任研究員)
- 助成金額
- 150万円
概要
重金属類は、地圏にありふれた元素であり、人為由来だけではなく、自然由来によっても、土壌・地下水汚染が引き起こされ、その環境基準超過率も高い。そのため、一つでも多くの有効な原位置浄化技術の開発が急務である。本研究では、別の汚染物質に実用化されている原位置加熱浄化技術が、重金属類にも適用可能かを検討するための基礎情報として、土壌に対する重金属類の吸着・脱離特性の温度依存性を評価した。実験試料として、黒ボク土、褐色森林土、沖積粘土層、海成シルト層の4試料を選定した。対象とした重金属類は、鉛、ヒ素とホウ素であり、20℃と40℃で、室内バッチ吸着試験を行った。ホウ素は、温度依存性が明確ではなかったが、ヒ素では、沖積粘土層と海成シルト層で、相対的に大きな温度依存性が確認された。すなわち、20℃よりも40℃で、吸着量が最大30%程度、増加する傾向が認められた。鉛では、あまり明確ではなかったが、海成シルト層で最大10%程度、20℃よりも40℃で、吸着量が増加する結果が得られた。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 原位置加熱浄化技術の開発に資する重金属類の吸着・脱離特性の温 度依存性評価 研...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
低利用を前提とした縮退期の地域環境計画手法に関する研究-東日本大震災被災地の事例から
- 研究者名
- 佃 悠
- 所属組織
- 東北大学大学院 工学研究科 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では、東日本大震災被災地を対象として、復興事業によって設けられた津波被害エリアの災害危険区域等の活用実態から、低利用を前提とした地域環境計画手法を検討したものである。調査から、中心市街地、市街地周縁部、集落・半島部でそれぞれ土地利用や維持管理の状況が異なることがわかった。集落・半島部などの防災集団移転促進事業移転元地は、一般的な利活用の視点からは活用可能性が低いが、そのような土地を住民組織が借り受けて、地域自治活動の構築や新しい産業の創出などにつなげていた。これらは、「利用価値」を前提としたこれまでの計画のあり方とは異なる、新たな価値を生み出すものであると考えられる。縮退期の計画手法は、不特定多数に向けた積極的な利用を促すための固定的なものではなく、住民の生活を起点として日常的な維持管理である「手入れ」の手法の選択肢を増やすものである必要がある。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 低利用を前提とした縮退期の地域環境計画手法に関する研究-東日 本大震災被災地...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
次世代交通サービスの導入による都市内モビリティ向上効果の数理的研究
- 研究者名
- 長谷川 大輔
- 所属組織
- 東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門 特任助教(東京大学大学院工学系研究科 特任助教)
- 助成金額
- 150万円
概要
CASE (Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)の技術革新による交通サービスの多様化・自動運転化・電動化の時代を見越し,①.都市内ネットワーク網の性能評価手法の開発を通じて,既存の固定路線・ダイヤ型の公共交通サービスの時空間的空白の所在を明らかにする.さらに②.多様な交通サービスの成立条件と都市内モビリティの向上可能性の評価を通じて,時空間的空白に該当する需要に対する新しいモビリティサービスの利便性向上効果を定量的に示し,CASE 時代の地域公共交通の設計指針について考察することで,将来的な社会的変革に対応した政策の具体的目標を示唆する.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 次世代交通サービスの導入による都市内モビリティ向上効果の数理 的研究 研究者...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 建築技術
3D スキャン・デジタルファブリケーション技術を用いた複雑形状の設計・製作方法論の実践的研究
- 研究者名
- 平野 利樹
- 所属組織
- 東京大学 総括プロジェクト機構 特任講師
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は3Dスキャン技術とAdditive Manufacturing(付加製造)に着目し、3Dスキャンの特徴の分析から、3Dスキャンモデルの複雑形状のデータ加工、デジタルファブリケーションのためのデータの最適化まで、一連のプロセスを検証するものである。
3Dスキャン手法の比較分析においては、フォトグラメトリと光投影法の2手法に着目し、それぞれのスキャンプロセスや結果の違いをもとに、各手法の特徴の分析を行った。
3Dスキャンデータを用いた複雑形状のファブリケーション手法の検討においては、3Dスキャンデータを組み合わせた複雑形状をデジタルファブリケーション加工データに変換する際の技術的課題を整理し、ディスプレイスメントマッピングを用いた形状の近似最適化手法を考案した。
上記のような検証をもとに、「情報量の膨大さの美学」という概念の考察を行った。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 3D スキャン・デジタルファブリケーション技術を用いた複雑形状の 設計・製作方法論...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 建築技術
ヨシを用いたストランドボードの高性能化および環境負荷低減効果の定量的分析
- 研究者名
- 永井 拓生
- 所属組織
- 滋賀県立大学 環境科学部 環境建築デザイン学科 講師
- 助成金額
- 150万円
概要
現在,我が国ではヨシの需要が縮退し,ヨシ群落の景観・環境保全のために新たな利用産業の創出が求められている。しかし,ヨシは基本的には人の手を要することなく生長するため,ヨシ刈りや野焼きといった定期的な管理行事を行うことで半永久的に調達が可能な持続可能素材と言え,加えて引張強度が高く,木質系構造用材料の原材料として実用性があると考えられる。
本研究では,ヨシの活用法の構築に向け,ヨシを原材料とした構造用ストランドボード(ReedStrand Board: RSB)の開発を目的とする。まず,構造用ヨシ製ストランドボードの基礎的な性能を実験により検証し,十分に実用可能性があることを確認した。次に,ヨシの特徴を意匠的に活かす新たなストランドボードの考案と試作,それを用いた実践的検証を行った。最後に,ヨシ製ストランドボードの製造過程におけるCO2 排出量の試算を行い,ストランドボードの原料としてヨシを用いることが環境負荷低減に一定の効果が期待できることを確認した。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) ヨシを用いたストランドボードの高性能化および環境負荷低減効果 の定量的分析...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
公営住宅団地を地域のコアとする産官学民による地域活性化システム
- 研究者名
- 橋本 彼路子
- 所属組織
- 長崎総合科学大学 工学部工学科建築学コース 教授
- 助成金額
- 97万円
概要
わが国の社会の高齢化は住まいや地域の環境に深刻な影響を与えている。今後のまちづくりに求められることは、住民にニーズに対応した魅力ある地域を個々に検討し創成していくことである。具体的には、高齢化の進む社会において老朽化高齢化が進む公営住宅団地ではその活力の乏しさは居住者にとっても深刻で、団地内には自治会が消滅した場所もあり、全国的に公営住宅団地の課題となっている。その解決に向け、様々な研究や検討を行うことは学術的にも有効なことである。実際に建替が決定した公営団地(県営K アパート)に対して、プロセスの初期段階から居住者に密着して、彼らのニーズを把握し、地域住民を中心としたまちづくりを創っていく可能性を検討した。2021 年12 月は感染症も小康状態になったことから、地域の高齢者が集まるイベントが約1 年ぶり開催されることになり、その会場でヒアリング調査を行うことで、コミュニケーションの場の有効性を検証することができた。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 公営住宅団地を地域のコアとする産官学民による地域活性化システ ム 研究者名※ 橋...
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。