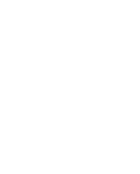検索結果一覧
821件中151件目から160件目を表示しています
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
デジタル道路地図を活用した車載移動設備に基づく都市路面管理システムの研究開発
- 研究者名
- 蘇 迪
- 所属組織
- 東京大学大学院 工学系研究科社会基盤学専攻 特任准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
多くの社会基盤の老朽化が進む近年,舗装路面の適切な維持管理の重要性が高まっている.そのため従来以上に,低コストで高頻度,かつ定量的に路面性状を把握することが求められる.申請者らは一般車両の振動応答を利用した路面評価システムを開発してき,車体に設置したスマートフォンにより車両の振動応答を計測することで路面評価を行う.本研究では,都市道路路面劣化に関わる道路属性・交通状況由来の影響要因を体系的に整理し,車載移動設備から構築された路面管理システムにおいて,計測条件に由来の変動要因を統計分析で解明し,先行研究で蓄積された路面計測データを適切な整理によって精度を向上させた.また車載移動設備で路面性状の識別可能条件を明確し,デジタル道路地図から確認した.さらに既存システムから識別できない路面変状において,車外音計測など新たな観測手法を用いて,鋼製伸縮装置の重大損傷検知の可能性を示した.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) デジタル道路地図を活用した車載移動設備に基づく都市路面管理シ ステムの研究...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
濃尾平野の扇状地における水田地帯の地下水涵養効果とその保全策
- 研究者名
- 神谷 浩二
- 所属組織
- 岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授
- 助成金額
- 148万円
概要
濃尾平野では,1994 年に経験したような異常渇水時の地盤沈下再進行に対処しながら地下水を水資源として持続利用するには,気象状況等によって変化する地下水涵養量に応じて地下水利用量を制御するとともに,地下水涵養機能を保全することが重要である.本研究では,濃尾平野の扇状地を対象に,水田の灌漑に伴う地下水涵養量やその機構を分析した.扇頂,扇央,扇端に位置する水田のそれぞれで浸透能を調査してそれに基づき地下水涵養量を評価する手法を検討した.更には,水田の作付状況と地下水涵養量の関係を考察した.そして,水田の作土層に比べると鋤床層の透水性が高い特徴が得られ,特に旧河道に位置する地点では鋤床層の透水性が高めになることが明らかになった.また,地下水涵養量は旧河道に位置して扇頂や扇央付近で多くなることが予測された.一方で,水田の水稲作付面積の減少に伴い地下水涵養量が減少傾向にあるが,耕作放棄地の湛水事業等の実施による地下水涵養量保全が期待された.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 濃尾平野の扇状地における水田地帯の地下水涵養効果とその保全策 研究者名※ 神谷 ...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
高齢歩行者が安心して横断できる交通環境整備の新しい考え方
- 研究者名
- 清田 勝
- 所属組織
- 佐賀大学 名誉教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、高齢歩行者の乱横断に着目し、それを防止するための具体的な対策を提案するとともに、その効果について検討したものである。乱横断の発生メカニズムを明らかにする場合あるいはモデル化する場合、さらには改善案を作成し、評価する場合などにおいて、どのようなネットワークを選択するかが特に重要になってくる。本研究では図-1 で示すような基本ネットワークを用いた。つぎに、高齢歩行者19名に横断時の安全性についてアンケート調査を実施した。その結果、横断歩道までの距離や信号が変るまでの時間が乱横断を引き起こす引き金になっていることが明らかになった。さらに、改善案を作成し、本対策がどの程度有効かを検討した。具体的には、連続する主要交差点の信号が両方とも赤になったとき、その間にある押しボタン式信号機の主道路の信号を赤に変更し(全赤)、車道部の横断禁止を解除すれば歩行者の交通環境は大幅に改善されることを実証実験と数値解析で明らかにした。さらに、この対策はどのような道路に適しているかもある程度判別できるようになった。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 高齢歩行者が安心して横断できる交通環境整備の新しい考え方 研究者名※ 清田 所属...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 建築技術
都市型集合住宅に使用される袖壁付きRC 柱の損傷変形評価に関する研究
- 研究者名
- 松本 豊
- 所属組織
- 久留米工業大学 建築・設備工学科 准教授(久留米工業大学 建築・設備工学科 教授)
- 助成金額
- 150万円
概要
近年、建物の耐震性能に対する要求水準が上昇して、例えば大地震後であっても無損傷または簡単な補修のみで復旧できるような性能を求められている。
このような要求に応えるためには、構造設計の際に地震動レベルに応じた建物の損傷を予測する必要がある。しかし、現在の設計では、設計時に詳細な損傷評価を行うことは困難である。これまでの研究では、主として部材や建物の耐力評価を主目的に実験が行われてきているが、変形性能や損傷評価に関する研究は殆ど行われていない。
先ず、実験により、袖壁が片側に取り付くRC 柱の変形およびせん断耐力を検証する。次に、解析アプローチにより骨組弾塑性解析を用いてブレース置換した部分にコリンズらの提案した修正圧縮場理論を組込み、実験で得られた変形およびせん断耐力と比較することで、袖壁付きRC柱の損傷評価可能な解析モデルを構築する。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 都市型集合住宅に使用される袖壁付き RC 柱の損傷変形評価に関す る研究 研究者名※...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
「同調」による自転車通行空間利用率向上に向けた基礎的研究
- 研究者名
- 三村 泰広
- 所属組織
- 公益財団法人豊田都市交通研究所 研究部 主幹研究員
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は多様な介入条件を提示した場合の意識面での反応程度を踏まえつつ、その反応をベースとした新たなフィールド実験を通じた検証を行い、より有益な同調による自転車通行空間利用率向上の知見を得ようとしたものである。WEBを通じた調査(n=824)並びに実フィールドを用いた検証(n=868)の結果、車道走行台数の多さが同調による車道選択を引き起こしやすいこと、車道選択者が女性の場合、より車道選択がされやすいなどの可能性を示した。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 「同調」による自転車通行空間利用率向上に向けた基礎的研究 研究者名※ 三村 泰広 所属...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
15・16 世紀フランスにおける木造町家に関する歴史考古学的研究とその保存・活用のための地方自治体の政策
- 研究者名
- 堀越 宏一
- 所属組織
- 早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授
- 助成金額
- 100万円
概要
15~16世紀のハーフティンバー式木造町家について、「宝珠状曲線装飾」と「十字窓」という特徴を手掛かりに、ノルマンディー・ブルターニュ両地方に現存する木造町家の所在を把握し、その分布、歴史的特徴、壁面の形状と構成、内部空間の構造を分析することを目指した。同時に、歴史的木造町家建築の保存と公開に関して、現地の自治体当局等による施策の調査も計画した。
コロナ流行により現地調査が行えず、文献とデータベースによる調査に留まった。成果としては、中世町家建築の3タイプとして、石造、木造、その混合型を区別し、その特徴を考察した。さらに対象地方各地に残されている中近世町家の新たな事例発見に努めた。今後は、木造町家に関する一次史料の収集に努める必要がある。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 15・16 世紀フランスにおける木造町家に関する歴史考古学的研究と その保存・活用の...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
長谷川逸子の公共建築における使い手の創造 山梨フルーツミュージアムを中心に
- 研究者名
- 平野 千枝子
- 所属組織
- 山梨大学大学院 総合研究部 准教授
- 助成金額
- 130万円
概要
長谷川逸子の公共建築では、住民との交流を重ねて設計を進める方法が先駆的に実践された。またそこでは、土地の歴史や現在のニーズをとり入れるだけでなく、その場所での活動を未来に向けて開いていこうとする工夫がなされていた。本研究は、長谷川のこうした建築の特質を個々の実践に即して考察した。特に、山梨フルーツミュージアム(1995 年)をとり挙げ、その建設の経緯、運営の変遷、使い手の活動を調査した。建築の創造的な可能性は、完結した作品のうちにあるのではなく、さまざまなネットワークのなかにある。建築の創造性を生かすには、このことを十分認識しなければならないだろう。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 長谷川逸子の公共建築における使い手の創造 山梨フルーツミュー ジアムを中心に...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
明治大正期広島の陸軍施設の配置計画と建築技術に関する研究―旧広島陸軍被服支廠倉庫を中心として―
- 研究者名
- 水田 丞
- 所属組織
- 広島大学 大学院先進理工系科学研究科建築学プログラム 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は広島市最大の被爆建物である旧広島陸軍被服支廠倉庫を中心として、被服支廠構内の施設の配置計画や倉庫の建築技術について考察したものである。
まず、戦前の地形図や航空写真、陸軍省の文書に含まれる古図面、聞き取りによって作成されたスケッチをもとに施設の復元配置図を作成し、施設配置の変遷や当時の様相を復元考察した。次に、現存する煉瓦倉庫の実測調査や復元調査を行い、実測平面図を作成、当時の仕様を復元した。また陸軍省の文書と比較することで、倉庫の平面計画を明らかにした。加えて、各地に現存する戦前に陸軍が建設した煉瓦造倉庫と比較し、旧広島陸軍被服支廠倉庫の位置づけを行った。広島の被服支廠倉庫は他の煉瓦造倉庫に比べて規模が大きく、一部簡略化された意匠を持ちながらも、石材を多用した意匠となることを明らかにした。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 明治大正期広島の陸軍施設の配置計画と建築技術に関する研究―旧 広島陸軍被服支...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
農村生活体験宿泊(教育旅行)による空き家古民家の群としての活用に関する研究~集落での体験宿泊モニターツアーの社会実験を通して~
- 研究者名
- 益尾 孝祐
- 所属組織
- 愛知工業大学 工学部 建築学科 講師(愛知工業大学 工学部 建築学科 准教授)
- 助成金額
- 150万円
概要
南会津町は、福島県の山間地にある町であり、「中門造り」と呼ばれる茅葺き屋根の古民家が数多く残存している地域である。しかし、過疎化の進行と共に、年々中門造り民家が減少してきており、地域の歴史的風致が失われつつある。近年、南会津町では、農村生活体験宿泊(教育旅行)の取り組みが行われており、コロナ禍の影響があるものの、今後の需要拡大が期待されている。しかし、現状の課題として、受け入れホストの高齢化に伴い、従来の「受け入れてくれるホストの家に泊まる」というモデルでは、持続性が低く、今後の宿泊需要の増加に対応しづらい状況となっている。本研究では、農村生活体験宿泊(教育旅行)の取り組み実態を明らかにすると共に、社会実験として、集落にある複数の古民家を活用し、農村生活体験宿泊(教育旅行)のモニターツアーを実施し「空き家となった古民家を活用して泊まる」という新たな事業モデルの確立を目指す。これらの取り組みを通して過疎地における空き家となった古民家の群としての活用について、新たな知見を得ることを目的とする。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 農村生活体験宿泊(教育旅行)による空き家古民家の群としての活 用に関する研究~集...
- 2020年度(令和2年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
都市構造物を利用した植物栽培環境の創出
- 研究者名
- 宮内 樹代史
- 所属組織
- 高知大学 農林海洋科学部 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
都市部での植物栽培空間を容易に創出することを目指し、被覆面の一部を建築物壁面で置き換えるプラスチックフィルム温室を提案した。まず対象となる建築物周辺の光環境の計測を行った結果、北面を除き東西南面で植物栽培が可能な光量子量が得られた。そこで、対象建築物東側面に小規模実験温室を設置し、温室内で植物栽培を行うとともに環境計測を行った。冬季夜間の温室内気温は外気に比して2~4℃高く推移し、栽培環境としてはやや厳しいものであったが、昼間は10℃以上高くなる場合もあり、対照温室と比較して昼夜間の温度差が大きい結果となった。試験品目としてトマト、イチゴ、ブルーベリー、ユズを無加温栽培したところ、いずれも対照温室(加温あり)と同等の生育を示した。特にブルーベリーにおいては、露地栽培に比して開花時期が1~2カ月早まり、早期収穫、収量増加の可能性が認められた。以上のことから、提案した温室は都市部での植物栽培空間として活用できることが示唆された。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2020 年度 研究課題(タイトル) 都市構造物を利用した植物栽培環境の創出 研究者名※ 宮内 樹代史 所属組織※ 高知大学 ...
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。