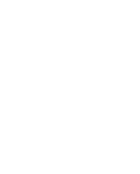検索結果一覧
821件中51件目から60件目を表示しています
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
大都市における遺跡の創造的な活用に関する研究:首都圏の事例
- 研究者名
- Drianda Riela Provi
- 所属組織
- 早稲田大学 社会科学部 準教授
- 助成金額
- 109万円
概要
本研究の目的は、大都市圏が遺跡、特に先史時代の遺跡をどのように保存し、都市住民の日常生活に利用できるようにするのかを明らかにすることである。首都圏をケーススタディとして、文献調査、現地観察、専門家へのインタビューを組み合わせて、先史遺跡が人々の日常空間となりうることを明らかにした。その結果、都市住民が先史遺跡を日常的に利用する要因として、以下の3点が挙げられた。それは、(i)アクセスしやすさ、(ii)場所の手頃さ、(iii)公共考古学の試みである。さらに、調査結果からは、遺跡への定期的な訪問者を増やすために、先史遺跡がとったいくつかの創造的なアプローチも発見された。本研究は、都市住民が日常空間として利用する可能性の高い先史時代の遺跡の特徴をより深く理解するために、より多くの遺跡を調査する必要性を示唆している。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 大都市における遺跡の創造的な活用に関する研究:首都圏の事例 研究者名※ Drianda Riela Provi 所...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 建築技術
RC造梁部材の変形・破壊メカニズムの詳細な解明
- 研究者名
- 浅井 竜也
- 所属組織
- 名古屋大学大学院 環境学研究科 助教(東京大学生産技術研究所 准教授 )
- 助成金額
- 150万円
概要
曲げ破壊型の鉄筋コンクリート造構造部材の変形・破壊メカニズムに関しては,主筋が降伏に至る比較的小変形時点までにおいても,斜めひび割れの発生や主筋-コンクリート間の付着力劣化など,部材全体の挙動に与える影響について十分な定量的理解が得られていない局所現象が残されており,このことは効果的に建築耐震性能を向上する上で妨げとなる。一方,近年高度化している計測システムは同部材の変形性状や内部鉄筋ひずみを高空間分解能で捉えることを可能とし,それらにより上記メカニズムの理解を大いに促進し得ることが近年の申請者の研究などにより示され始めている。そのため本研究では,曲げ破壊型の梁部材の静的載荷実験において,同部材の変形・破壊過程時の変形・ひずみ分布を詳細に計測した。それにより,上記現象の発生性状と,それによる部材内ひずみの古典理論(平面保持仮定)との差異,さらに,それが部材耐力に及ぼす影響を定量的に把握した。今後は,同影響を評価するマクロモデルについて,終局状態まで含めて検討する。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) RC 造梁部材の変形・破壊メカニズムの詳細な解明 研究者名※ 浅井 竜也 所属組織※ 名古屋...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
高齢者等の継続歩行距離を考慮したシティベンチの逐次配置方法の開発
- 研究者名
- 薄井 宏行
- 所属組織
- 東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻 助教(千葉工業大学 創造工学部 都市環境工学科 教授)
- 助成金額
- 135万円
概要
歩行は高齢者の身体活動の基礎であり,健康の維持に欠かせないものである.高齢社会において,高齢者が無理なく徒歩で移動できる都市空間の実現は喫緊の課題である.本研究の目的は,高齢者等の継続歩行距離を考慮したシティベンチ(以降,「ベンチ」と記す.)の配置方法を開発することである.継続歩行距離とは,歩行者がベンチ等で休むことなく継続して歩行できる距離である.一般に,高齢になるほど,継続歩行距離は短くなる傾向にある.高齢者が無理なく徒歩で移動できるような都市空間を実現するために,ベンチを適切に配置することは極めて重要である.ベンチの配置が不足している地域では,新たにベンチを増設する必要がある.ところが,ベンチの配置間隔等の基準や方法は具体的に定められていない.本研究の意義は,厳しい予算制約の下で,「どこに,どのような順序で,ベンチを増設すべきか」という問題を解決する方法を定量的かつ具体的に示し,高齢者にとって歩きやすい都市空間の実現に貢献することにある.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 高齢者等の継続歩行距離を考慮したシティベンチの逐次配置方法 の開発 研究者名※...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 建築技術
AI(人工知能)による透水性コンクリートの空隙率推定に関する研究
- 研究者名
- E RIDENGAOQIER
- 所属組織
- 東京理科大学 工学部 建築学科 嘱託助教
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では,人間の経験による学習を再現する「人工知能(AI)」技術を導入することで,ポーラスコンクリ-トの空隙率を誰でも簡単に精度よく推定する方法を開発することを目的とし,ディープラーニングによる画像分類を用いて透水性コンクリ-トの空隙率の推定を行い,測定確率を確認した。その結果,ディープラーニングによる画像認識技術を適用することでポーラスコンクリ-トの空隙率をある程度高い確率で推定可能であることが明らかになった。また,その推定確率は,学習用画像の画素度およびディープラーニングのエポック数(学習回数)の影響を受けることが確認された。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) AI(人工知能)による透水性コンクリートの空隙率推定に関する 研究 研究者名※ E RIDENGAOQIER 所...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
コミュニティ交通導入による外出促進がもたらす経済的・健康的効果の評価方法に関する研究
- 研究者名
- 西堀 泰英
- 所属組織
- 大阪工業大学 工学部都市デザイン工学科 特任准教授(大阪工業大学 工学部都市デザイン工学科 准教授)
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究の目的は,生活の足を確保することによる外出促進効果だけでなく,買い物や外食等の消費増による経済的効果や,身体活動量や交流の増加等による健康増進効果などの多面的効果を評価することである.愛媛県松山市の定額制移動サービスを対象とし,アンケート調査や交通ビッグデータを用いた外出促進効果の把握と,心の健康状態変化の把握,家計簿調査による総消費額変化を把握した.その結果,外出促進効果については,単純に外出回数が増えたことだけでなく,潜在化していた外出需要が,サービス導入後に顕在化したことも確認した.交通ビッグデータを用いた分析では,既存公共交通がカバーできていない空間や時間を埋めるように移動サービスが提供されていることを確認した.また,健康増進効果については心の健康の観点で,幸福感が増大した効果が確認できた.経済的効果については,限られたサンプルではあるが消費額の増加を確認できたが,引き続き検証が求められる.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) コミュニティ交通導入による外出促進がもたらす経済的・健康的 効果の評価方法に...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
子どものスケートボードの遊技・競技と都市空間の環境整備に関する研究
- 研究者名
- 小関 慶太
- 所属組織
- 八洲学園大学 生涯学習学部 生涯学習学科 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
子どもの権利条約第31条を根拠として、子どもの遊び・競技としてのスケートボードを行う上での問題点として、都市にある空間の1つとしての「公園」「専用パーク」とその公園の環境や理解について理論及び観察調査研究を行った。
結果としては、空間に対しての安全安心を第一成果とした環境犯罪学的な見地、子どもの最善の利益や健全育成を第一目標とする遊び優先の考え方、市民の平穏性とが交錯している。
都市空間の環境整備は、他者が他者を思いやり、対話(コミュニケーション)が必要になってくる。また場合によっては必要的公権力の介入により環境整備を行う必要性がある。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 子どものスケートボードの遊技・競技と都市空間の環境整備に関 する研究 研究者名※...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
日本・韓国における都市景観施策の誘導手法に関する研究
- 研究者名
- 坂井 猛
- 所属組織
- 九州大学 本部キャンパス計画室・大学院人間環境学府 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
近年はアジア諸国の積極的かつ大規模な事例の応募が急増している。都市景観を早期に認識するか否かによって、都市の将来象が大きく変わり、土地の価値、都市のブランド力、観光客誘致に影響することを認識し、多くの都市が景観施策を重視するようになっている。これまでの欧米主体の景観誘導に対して、アジアならではの評価基準や誘導手法があるのではないか。持続可能な社会に向けて、コロナ禍を経て、テレワークの進展とともに地方回帰の流れが進むことが予測されるなかで、諸都市の特徴を活かした魅力ある都市景観を適切なかたちで形成する施策のあり方を問い直したい。本研究は、都市整備事業が展開する日本と韓国における都市景観施策(景観計画とガイドライン、誘導手法等)の比較分析を通して、景観施策の特徴と課題を明らかにすることを目的にしており、日韓の都市景観施策の発展段階・タイムライン上の位置づけと歴史的、地理的特徴。①都市景観施策としての景観計画とガイドラインの特徴と課題等を明らかにした。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 日本・韓国における都市景観施策の誘導手法に関する研究 研究者名※ 坂井 猛 所属組織※...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
鉄道軌道の簡易な予防保全に関する研究
- 研究者名
- 藤田 吾郎
- 所属組織
- 芝浦工業大学 工学部電気電子学群電気工学科 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
軌道管理の本質は,軌道変位設計値からの差 を定量的に把握することである。この計測には軌道試験車を用いる方法と手作業による方法に大別される。前者は高価であり,採用できるのは十分な資金力のある,限られた大手鉄道事業者に限られる。後者は正矢法と呼ばれる方法であり,水糸を張ってレールの相対的な位置関係を計測していく方法である。こ れには膨大な人手を介するのが弱点であり,例えば30kmの路線の検測のために3名・3か月を要する。
本グループでは,地方鉄道会社での安全性向上を目的として低コストかつ簡便に軌道の異常検知が可能となるシステムの構築を研究している。今回は測定方法に改良を施すとともに,速度別のデータの扱い方を,乗り心地の評価への適用も含めて検討した。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 鉄道軌道の簡易な予防保全に関する研究 研究者名※ 藤田 吾郎 所属組織※ 芝浦工業大学 ...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
都市の近代化と街灯の建設
明治期の港町新潟における街灯の構造と補修について
- 研究者名
- 菅原 邦生
- 所属組織
- 新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、明治期における港町新潟の街灯について、その構造や建設後の補修について、港町新潟の建設整備過程との関係から分析し、開港場における街灯の果たした役割を明らかにすることを目的としている。都市施設の一つに過ぎない街灯の建設整備過程を検討することが、都市の近代化を捉える上で有用なのは、その建設の経緯が、開港場の建設整備過程と密接に関係しているためである。新潟は横浜・神戸などと異なり、外国人居留地のない雑居地のみの開港場であり、外国人に恥ずかしくない市街地とするため、早急な街路空間整備が求められた。そのため早期建設が可能となるよう街灯の構造は単純で、風紀粛清や防犯を目的としていた。設置数も当初の275基から、明治16年(1883)には304基となり、ペンキ塗や破損個所の修繕など、徹底した補修が行われた。当初から恒久的なものではなく、早急な建設を優先したためである。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 都市の近代化と街灯の建設 明治期の港町新潟における街灯の構造と補修について...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
歩行者と自転車及び自動車が混在する通学路の交通環境改善手法の提案
- 研究者名
- 梶田 佳孝
- 所属組織
- 東海大学 建築都市学部土木工学科 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、歩行者や自転車及び自動車交通が混在する危険な状況を三者が共存する安全で、便利な交通環境に改変するための方法を提案し、その有用性について検討したものである。交通事故を減らし、安全な交通環境にするためには、次の二つの対策が有効である。➀各交通手段の分離、②自転車の一方通行化。安全性を確保することは必要であるが、その他にも大切なものがある。それは直線性(直線的に行ける)の確保である。迂回しないでダイレクトに横断するには、両側の赤時間を利用して車道部を横断させることが必要である。図-1 に示すように連続する二つの交差点の信号が赤になった時、その間にある押しボタン式信号機の信号を赤にすれば、すべての信号が赤になる。その結果、この区間の交通量が減少するので、横断の機会は増加する。従来の対策と今回提案した対策の基本的考え方を説明した調査票を用いた意識調査を実施した結果、住民の多くが現状に不満を持っていること、及び今回提案した安全対策に対する評価は高く、今後の有効な対策として十分期待できることがわかった。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 歩行者と自転車及び自動車が混在する通学路の交通環境改善手法 の提案 研究者名※...
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。