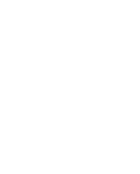検索結果一覧
821件中71件目から80件目を表示しています
- 2022年度(令和4年度)
- 奨励研究
- その他
オフィス供給の地理的分布と波及効果に関する時空間分析
- 研究者名
- 松尾 和史
- 所属組織
- 筑波大学大学院 理工情報生命学術院システム情報工学研究群 不動産・空間計量研究室
- 助成金額
- 80万円
概要
本研究の目的はオフィスビルの新規供給の特徴を整理し、新規供給がオフィス市場に与える影響を定量的に明らかにすることである。はじめに、オフィスビルのストックおよび新規供給の地理的な分布から、その特徴を整理した。次に、大規模オフィスビルの新規供給に焦点をあて、近隣の賃料にどの程度の影響を与えるのか、因果推論の手法を用いて、定量的な分析を行った。最後に、エリア間のオフィスマーケットの動態に着目し、エリア間・規模間の市場の相互依存関係について、モデルの定式化と探索的な分析を試みた。
分析の結果、近年の新規供給は、面積の大きな上位数棟の大規模オフィスビルがその大半を占めており、特定のビルの影響が大きいことがわかった。また、大規模オフィスビルの新規供給が近隣の賃料に及ぼすは軽微であり、立地によってその影響が異なることが明らかになった。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) オフィス供給の地理的分布と波及効果に関する時空間分析 研究者名※ 松尾 ...
- 2022年度(令和4年度)
- 奨励研究
- その他
生闘学舎(1981年建築学会作品賞)の屋根材更新に伴う設計構法に関する実測研究 -枕木組積を用いた自力建設物に内在する伝統技法の調査-
- 研究者名
- 徐 子
- 所属組織
- 早稲田大学大学院 創造理工学研究科 中谷礼仁研究室
- 助成金額
- 80万円
概要
生闘学舎・자립(以降、生闘学舎と略す)は、三宅島にて約5千本の中古の鉄道用枕木を建材として組積された建造物である。夜間学校設置運動や全共闘運動に参加してきた髙野雅夫を代表格とした素人の集団建設によって、建築家・高須賀晋の建築設計ならびに同島の棟梁・宮下英雄の技術指導にもとづき、1975年から1980年までの年月を費やし実現した。1981年に同建造物が建築学会作品賞を受賞するなど、日本近現代建築史にとって重要な作品である。本研究は同建築の設計段階における意図と施工段階における実際を考察する。まず、図面分析によって、設計過程における枕木の扱い方を解読し、建築基準法関係法令における壁量計算と枕木の寸法によるモジュールが同建築の形態的特徴を形成した2つの根拠であることを明らかにした。また、実測及び模型製作(進行中)を通じ、施工過程における変更箇所と枕木の加工方法を検討し、施工的見地からの考察を加える予定である。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 生闘学舎(1981 年建築学会作品賞)の屋根材更新に伴う設計構法 に関する実測...
- 2022年度(令和4年度)
- 奨励研究
- その他
インフラとともに生きる : 高架下の空間管理と土地利用形態に関する比較研究
- 研究者名
- Barua Srijon
- 所属組織
- 京都大学大学院 地球環境学舎 人間環境設計論
- 助成金額
- 80万円
概要
交通インフラは、その経路上に多数の残余空間(高架下の空虚な負の空間)を生成する。私の研究は、このような高架橋が生み出す空間における空間利用の多様な類型とアクセシビリティのパターンに光を当てることを目的としている。このインターンシップは、ヨーロッパとイギリスの都市における高架橋下空間の管理慣行と進化の過程を掘り下げる貴重な機会となる。何世紀にもわたるヨーロッパの豊かな高架橋建設の歴史は、高架橋の管理手法の進化や、高架橋が都市景観に与える影響を明らかにする豊富なケーススタディを提供している。スイスのチューリッヒ工科大学(ETH Zurich)とイギリスのバートレット大学(Bartlett-UCL)でのインターンシップでは、チューリッヒとロンドンの高架橋の成長と土地利用のパターンを、特に地元のケーススタディに焦点を当てて調査する。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 奨励研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) インフラとともに生きる : 高架下の空間管理と土地利用形態に関 する比較...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 都市交通システム
- エネルギー計画
日本版シュタットベルケのあり方に関する研究
- 研究者名
- 大塚 彩美
- 所属組織
- 東京家政大学 家政学部 環境教育学科 特任講師(東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員)
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では、岡山県真庭市を対象として地域住民に対するアンケート調査と需給データベースの構築、それに基づくシナリオ分析によるシュタットベルケ型ビジネスモデルの実現可能性を検討した。アンケート調査では地域サービス重視の地域電力会社への受容度の割合が高いにもかかわらず、電力会社切替え・検討したことがある人の割合が他調査と比較して低く、地域電力会社の切り替え方法も含めて認知が広まれば切替えポテンシャルが高まると考えられた。真庭市内の久世の家庭を対象としたシナリオ分析では、バイオマス1200kW、住宅25%、業務1000kWの十分な再生可能エネルギーの導入により、2020年時のデータで全体需要の68.3%を賄うことができ、年間約2.4億の地域循環額、会社として648万円の利益のある地域電力会社の実現が可能と試算された。今後は分析対象の拡大・深化により、市民の電気料金の負担や地域サービスと経営のバランスを踏まえたシュタットベルケ型電力会社の実現可能性の検討が可能になると考えられる。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) 日本版シュタットベルケのあり方に関する研究 研究者名※ 大塚 彩美 所属組織※ 東京家...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 建築技術
タワー建築における避難情報システムの構築に関する研究
- 研究者名
- 山邊 友一郎
- 所属組織
- 神戸大学大学院 工学研究科 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究は、神戸ポートタワーを対象として、地震や台風などの災害発生時に、施設利用者の避難の必要性を判別し、避難させる際には施設利用者の安全かつ迅速な避難を支援する情報システムの構築を目的とする。そのために、①構造特性の把握、②避難行動実験によるエージェントモデルの作成、③マルチエージェントシミュレーションによる避難誘導システムの提案、の3つの研究課題を実施した。その結果、対象建物の固有振動モードを明らかにし、避難者の歩行モデルを作成し、また、「安全性」と「迅速性」を共に満足するためには順次避難が有効である、などの知見を得た。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) タワー建築における避難情報システムの構築に関する研究 研究者名※ 山邊 友一郎 所...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
高速道路凍結防止剤の流入がカワシンジュガイの生息に及ぼす影響
- 研究者名
- 辻 盛生
- 所属組織
- 岩手県立大学 総合政策学部 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
寒冷地の高速道路には、冬期の交通事故防止策として凍結防止剤(塩化ナトリウム)散布が行われる。高速道路排水には、時には海水濃度を超える塩化ナトリウムが含まれ、中小河川に濃度変化を与えることが明らかになった。岩手県滝沢市の小河川には、希少種であるカワシンジュガイが生息し、高速道路排水による影響が懸念される。特に、カワシンジュガイの繁殖期である気温が上昇し雪解けが進む時期に負荷量が増加し、カワシンジュガイの再生産阻害の要因である可能性が示唆された。高速道路排水には、他に生態毒性を有する亜鉛や銅、6PPD-Q(タイヤの劣化防止剤の酸化物質)が確認された。面源負荷とされる高速道路排水であるが、処理が困難な点源負荷としての性格を有する。流れ込む小河川に水質的側面から生態的な影響を与える可能性があることから、流出後に水環境への影響を減らす工夫が必要である。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) 高速道路凍結防止剤の流入がカワシンジュガイの生息に及ぼす影響 研究者名※ 辻 盛...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
インドネシア地方都市の環境保全を目指したバティック廃水処理装置
- 研究者名
- 惣田 訓
- 所属組織
- 立命館大学理工学部 環境都市工学科 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
バティック廃水の処理施設が未導入な地方都市の産業と環境保全を目指し、高コストであるが処理が確実と思われるオゾン処理と、低コストであるが処理が不安定と思われる人工湿地によるバティック廃水の処理技術の開発を目的とした。染料としてリアクティブブラック5(RB5)とリアクティオレンジ16(RO16)を含む廃水のTOC濃度は、オゾン処理単独では、それぞれ8.9mg/Lから5.8mg/L、13.9mg/Lから7.1mg/Lとなり、35~49%も減少した。さらにオゾン処理後に生物分解を組み合わせることで、RB5とRO16を含む廃水のTOC濃度は、3.3mg/Lと4.0mg/Lとなり、63%と71%も減少した。人工湿地による処理実験では、滞留時間5日、廃水中の染料リアクティブイエロー86(RY86)の濃度を10~50mg/Lにおいて、砂利系で約10~25%、ガマ砂利系で約40~80%、パピルス砂利系で約70~90%と、植栽系で高い除去率が得られた。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) インドネシア地方都市の環境保全を目指したバティック廃水処理装 置 研究者名※ 惣...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
過去の自然災害におけるモスクの支援活動に関する学際的調査研究
- 研究者名
- 小谷 仁務
- 所属組織
- 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 助教
- 助成金額
- 150万円
概要
言語や宗教などの点でマジョリティと文化・社会的相違をもつ外国人は「災害弱者」に含まれる傾向にある。その一方で、外国人の中でも災害時に被災地で活躍したことが報告される者たちが存在する。イスラ-ム教の礼拝所「モスク」を中心とするコミュニティである。本研究は、近年の自然災害におけるモスクによる短期・長期の支援活動の実態を総括的に明らかにすることを目的とする。そのために2011年東日本大震災と2016年熊本地震の被災地に立地する3つのモスクについて、既往文献の整理と共にモスク管理者・代表者へのインタビュー調査を実施した。結果として、概してモスクは短期の応急活動において救援物資の収集・供給拠点として機能していることが分かった。マイノリティ外国人のニーズに沿う食事や情報の提供だけでなく、マジョリティの日本人へも支援を行っていた。炊出し施設や避難所として機能しうるものもあった。一方で、長期の復興活動(住宅再建・転居のための相談窓口、金銭的支援の実施、自治体への寄付など)は特に実施されていなかった。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) 過去の自然災害におけるモスクの支援活動に関する学際的調査研究 研究者名※ 小谷 ...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
人工知能による無電柱化三次元空間情報の作成
- 研究者名
- 山本 義幸
- 所属組織
- 愛知工業大学 工学部 土木工学科 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
日本の戦後復興の過程で,送電のために電柱利用が一般化し,景観を悪化させた現状に対し,防災もあいまって無電柱化への期待が高まっている.無電柱化の具体的なイメージを住民に提示することは,関連工事への理解を促す有効手段だが,従来の技術では専門性が必要である.例えば,自動的に大量の三次元点群情報から電柱を特定し削除し,無電柱化された三次元空間情報を生成することは作業コストが高い.こうした技術的課題に対して,本研究は人工知能を利用して,画像から電柱を抽出し,その部分を周囲と違和感なく塗りつぶすことで無電柱化イメージ画像を作成し,それらをSfM(StructurefromMotion)を利用して無電柱化の三次元空間情報を作成した.SfM処理で,人工知能による無電柱化画像では位置的な整合性が完全には保たれない部分もあったが,元画像から得られたカメラ位置を利用することで部分的な三次元点群を生成することができた.これにより,無電柱化三次元空間情報作成のための新たな効果的な手法を提示できた.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) 人工知能による無電柱化三次元空間情報の作成 研究者名※ 山本 義幸 所属組織※ 愛知工...
- 2021年度(令和3年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
若年自営業者による空き家・空き店舗の活用による都市コミュニティ形成の研究
- 研究者名
- 富永 京子
- 所属組織
- 立命館大学 産業社会学部 社会学研究科 准教授
- 助成金額
- 100万円
概要
本研究の目的は、空き家・空き店舗の再利用を中心とした若年自営業者による都市コミュニティの形成過程と、そのコミュニティがもつオルタナティブな社会的・政治的可能性を明らかにすることである。関東・関西における都市コミュニティを検討したところ、主として①企業との雇用関係による従来の働き方と異なるオルタナティブな労働への志向、また②地域住民とのネットワーク形成、③マイノリティの包摂に重点を置く点が明らかになる一方、先行研究で論じられてきた民主的な参加によるコミュニティ維持や外部補助については重要視されていないことが明らかになった。また今後の課題として、セルフビルドという手段をなぜ用いているのかという問いへの建築面からのアプローチ、またジェンダーやマイノリティの観点から見た職住空間という観点からの検討がより重要であると考えられる。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2021 年度 研究課題(タイトル) 若年自営業者による空き家・空き店舗の活用による都市コミュニテ ィ形成の研究 研...
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。