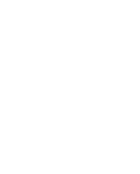検索結果一覧
821件中41件目から50件目を表示しています
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
戦後日本の都市開発についての政治史研究:港湾から臨海部への転換
- 研究者名
- 稲吉 晃
- 所属組織
- 新潟大学 人文社会科学系 教授
- 助成金額
- 112万円
概要
本研究は、1950年代末から1960年代にかけての大分臨海部開発を検討することにより、日本の地方都市においてどのように臨海部が開発されてきたのか、また中央政府と地方政府の意向がどのような場合に合致して強力に政策が推進されるのか、解明しようと試みるものである。
本研究により、①戦後の臨海部開発の計画をめぐっては、戦前からの土木技師のネットワークにより、その構想が共有されていたこと、②山間地や盆地が多いという大分県の地理的特徴により、大分県からは多様な人材が全国区に輩出され、そのネットワークは政官財界にひろがっていたこと、③この地理的特徴は、臨海部開発の候補地がひとつしかないことを意味しており、県内の対立が生じにくかったこと、④中央・地方に広がるネットワークは、県知事を中核として有効に機能した場合に有効に機能し、政策が強力に推進されること、の4点が明らかになった。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 戦後日本の都市開発についての政治史研究:港湾から臨海部への 転換 研究者名※ 稲吉 ...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市環境工学
豪雨に起因した河川堤防崩壊機構に関する研究
- 研究者名
- 金澤 伸一
- 所属組織
- 新潟大学 工学部工学科社会基盤工学プログラム 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では,近年頻発している突発的な集中豪雨による河川堤防の破堤事例を背景に,堤防が破壊に至るメカニズムに焦点を当てた.特に,河川堤防の破堤の約7割が越水によるものとされている中,降雨による外水位の上昇速度が堤防の内部構造にどのような影響を及ぼしているか解析を実施する.
特に,不飽和土/水/空気の三相連成問題として堤防の力学挙動を解明し,施工後の降雨や豪雨による外水位変動が堤体内の応力挙動に及ぼす影響をシミュレーションによって明らかにする.さらに,堤防が破壊に至る降雨量と外水位変動速度の関係を定量的に明らかにすることで,河川堤防の長期的な安定性向上に貢献することを目指す.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 豪雨に起因した河川堤防崩壊機構に関する研究 研究者名※ 金澤 伸一 所属組織※ 新潟大...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
戦後日本の建築家・ゼネコンによる東~東南アジア・プロジェクトに関する歴史研究
- 研究者名
- 市川 紘司
- 所属組織
- 東北大学大学院 工学研究科 都市・建築学専攻 助教
- 助成金額
- 150万円
概要
戦後日本がその経済活動をアジア領域へと展開するなかで、日本の建築家やゼネコンによる建築もまたアジア各地で建設されるようになる。資本主義グローバリズムが進展する現代においては、なおさらこうした建築の国際化は進んでいる。本研究では、文献調査・実地調査・聞き取り調査をつうじて、戦後日本の建築家およびゼネコンが東〜東南アジアで実施してきたプロジェクトの全体像とその歴史的変遷、および他国との比較をつうじてその相対的な位置づけを了解した。グローバリズムの進展とともに、建築の生産システムや文化は一国単位で閉じることなく相互に連関する。本研究は、戦後アジアの近現代建築史を地域単位で構想するための基礎的作業であると位置づけられる。また、戦後世界を二分した冷戦構造が建築文化におよぼす影響の検討作業としても意味をもつものだと考えられる。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 戦後日本の建築家・ゼネコンによる東~東南アジア・プロジェク トに関する歴史研究 研...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市建築史
- 都市と文化
建築光環境・視環境設計における3D都市データの利用
- 研究者名
- 古賀 靖子
- 所属組織
- 九州大学大学院 人間環境学研究院 都市・建築学部門 准教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では、3D都市データを利用して、計画建物とその周辺地域をゲームエンジン上で表現し、計画建物の窓から見える屋外地物の様子を可視化し、その輝度マップを深層学習により生成する方法の開発を目差す。主要課題は、3D都市データのテクスチャ画像の色情報から、地物の反射率を推定することである。一般に、テクスチャ画像取得時の測光条件は不明のため、全天球カメラによる測光データを補助的に用いる。
まず、全天球カメラによる測光のために、全方位画像の画素値から輝度を推定する式を求めた。これより、全天球カメラを搭載した小型無人航空機と地上からの画像による測光を可能にした。次に、建物外壁を2方向から同時に撮影した全方位画像より、反射特性を調査した。輝度マップには、地物反射光の拡散反射成分が必要であり、直射日光の鏡面反射成分は別に扱い、空中または地上から得た測光データを参照して、輝度マップの生成が可能であることを明らかにした。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 建築光環境・視環境設計における 3D 都市データの利用 研究者名※ 古賀 靖子 所属組織※ 九...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
東京大都市圏における母親の生活行動からみた子育てと仕事の両立可能要因
- 研究者名
- 佐藤 将
- 所属組織
- 東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所 研究機関研究員(金沢星稜大学 経済学部 講師 )
- 助成金額
- 100万円
概要
これまでの母親の保育送迎を含んだ通勤行動の検証からは、子どもの有無が判断できないため、子育て世帯に絞った送迎・通勤行動の実態解明は難しかった。そこで本研究では子育て世帯であるか否かが判断可能な「東京都市圏ACT」データおよびアンケート調査を用いて、コロナ前後における子育てと仕事の両立実現者の日常的な生活行動の特徴について保育送迎を含んだ母親の通勤行動から明らかにする。コロナ前の調査から東京都区部に居住する子育て中の母親の保育送迎を伴う通勤行動は勤務先が都心3区や新宿をはじめとしたオフィス街であり、通勤距離も長くなっている傾向にあった。それに併せてフルタイム就業者自体も多くなっている傾向が明らかとなった。コロナ後においてはアンケート調査を行い、特に夫婦間での保育送迎の分担状況について調査を行った。その結果、多くの母親がお見送り・お迎えともに自分自身で行っており、依然として母親の負担が大きいことが明らかとなった。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 東京大都市圏における母親の生活行動からみた子育てと仕事の両 立可能要因 研究...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
原発避難市町村の復興まちづくりに関する研究
- 研究者名
- 川﨑 興太
- 所属組織
- 福島大学 共生システム理工学類 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
2011年3月の福島原発事故の発生に伴って原発の周辺に位置する12市町村(以下「原発避難市町村」)には避難指示が発令され、住民は長期にわたって避難を余儀なくされた。その後、除染やインフラの復旧・再生等が実施されたことによって、2020年3月までに避難指示は帰還困難区域を除いて解除され、住民は法的・制度的にはふるさとに帰還することが可能になった。しかし、ふるさとに帰還した住民は、福島原発事故から11年が経過しても約2割にとどまっており、原発避難市町村は存続の危機に陥っている。本研究では、こうした状況にある原発避難市町村を対象として、原子力災害からの復興まちづくりの実態と課題を明らかにすることを目的として、福島復興政策の変遷と学説に関する調査・分析、復興まちづくりの実態に関する調査・分析、帰還者と避難者の生活再建に向けた課題の抽出に向けた調査・分析を行った。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 原発避難市町村の復興まちづくりに関する研究 研究者名※ 川﨑 興太 所属組織※ 福島大...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
長崎市東山手・南山手地区における歴史まちづくり計画のためのデータ分析に関する研究
- 研究者名
- 平岡 透
- 所属組織
- 長崎県立大学 情報システム学部 情報システム学科 教授
- 助成金額
- 100万円
概要
本研究では、長崎市東山手・南山手地区における歴史まちづくり計画への寄与と、長崎市の観光振興を目的として、アンケート調査を基に大きく二つのデータ分析を行った。
一つ目の研究(以下、研究1)では、重点区域内の住民と重点区域外の市民に対するアンケート調査を行い、東山手・南山手地区内外での住民と市民の意識の差異を年代別に統計的手法を用いて分析した。また、東山手・南山手地区内外のそれぞれで年代間の住民および市民の意識の差異も年代別に分析した。
二つ目の研究(以下、研究2)では、長崎市への旅行者の訪問地と満足度をアンケート調査で調査し、訪問地の有無と満足度の関係を統計的に分析した。また、稲佐山展望台と鍋冠山において、夜景観賞の有無と満足度の関係も分析した。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 長崎市東山手・南山手地区における歴史まちづくり計画のための データ分析に関す...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市計画
- 都市景観
都市拠点の人流パターン解析と市街地構造変容のモデル分析研究
- 研究者名
- 鈴木 勉
- 所属組織
- 筑波大学 システム情報系 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では,都市拠点における毎日の人流特性を分析し,その特徴を把握することで,都市拠点の発展プロセスを理解し,市街地の更新速度と容積変化をモデル化して将来の都市変容を予測することを目的とする.都市の拠点地区における人流パターンの解析については,平日と土休日の人流パターンの時間変動に基づき街区・商業集積地・町丁目の3レベルで地区を類型化し,街区は土地利用用途構成,商業集積地は業種構成,町丁目は土地利用混合状況や建物・道路特性と有意な対応関係があることを示した.また,類型ごとに街区の滞在時間や移動距離,および商業集積地の滞在者数や圏域に特徴があることを明らかにした.市街地更新速度と容積率変化のモデル分析では,土地利用データの時系列分析を通じ,東京区部全体での容積率及び,集合住宅の増加を明らかにするとともに,安定した人口構成を維持する3地区を比較し,人口構成と市街地更新の関連性を示し,市街地の成熟度や容積率の関係をモデル化するための基礎データを得た.
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 都市拠点の人流パターン解析と市街地構造変容のモデル分析研究 研究者名※ 鈴木 勉...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
東アジアにおける社会的不利地域の居住支援に向けたアクションリサーチ
- 研究者名
- 全 泓奎
- 所属組織
- 大阪公立大学 都市科学・防災研究センター/現代システム科学研究科 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
近年、新たな貧困問題の拡大に対し、「社会的排除」という概念への関心が高まっている。本研究では、このような新たな貧困概念が、個人や世帯を介して地域への影響として現れる場合や、貧困地域にかかわる地域による負の影響にも注目することが必要であると思われることから、とりわけ東アジアの国や地域に焦点を当て、各々の都市内の社会的不利地域を対象とした居住支援のモデルを構築するための調査研究を進めた。調査対象地域は、東京の山谷地域、大阪のあいりん地域(通称「釜ヶ崎」)の他、国外では韓国のチョッパン地域、そして台湾の台北市内の萬華区を中心とした元ホームレスの人びとの居住する地域である。本研究では、文献等を用いて当該地域の形成史を調査し、行政や民間の支援団体等による当該地域にかかわる統計データや、施策展開・民間独自の支援プログラムを知るための行政や支援団体へのインタビュー調査を行った。また、居住支援のニーズにかんしては、各地の居住当事者へのインタビュー調査を行った。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 東アジアにおける社会的不利地域の居住支援に向けたアクション リサーチ 研究者...
- 2022年度(令和4年度)
- 研究助成
- 都市政策
- 都市経済
市民の合意形成スキルの向上を目的にしたゲーム教材の開発
- 研究者名
- 濱田 栄作
- 所属組織
- 琉球大学 教育学部 教授
- 助成金額
- 150万円
概要
本研究では,仮想の島における高レベル放射性廃棄物の地層処分場建設地域を選定するゲーム教材「New HLW」を開発し,処分地選定に関する合意形成を模擬体験できる授業を,次世代を担う中学生を対象に実施した。実施後のアンケート結果によると,9割以上の生徒が「地層処分について興味関心が高まった」,7割を超える生徒が「今後社会的な課題解決に向けた討論に参加したい」と回答したことから,「New HLW」は地層処分について興味・関心を持たせ,社会的課題に関わる態度の育成に有効であると考えられた。また,9割近くの生徒が「根拠をもとに相手に説明する事ができた」と回答し,さらに,討論中においても補足的に情報収集を行いながら複数の根拠をもとに,活発な討論活動が行われていた。これらのことから,本教材は根拠をもとに相手に説明し,異なる立場の相手と合意形成を図る態度の育成に有効であり,本教材は活用することで合意形成スキルの向上が期待される。
キーワード該当箇所
...公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 公益財団法人大林財団 研究助成実施報告書 助成実施年度 2022 年度 研究課題(タイトル) 市民の合意形成スキルの向上を目的にしたゲーム教材の開発 研究者名※ 濱田 栄作 所...
掲載されている氏名・所属組織は申請当時のものです。